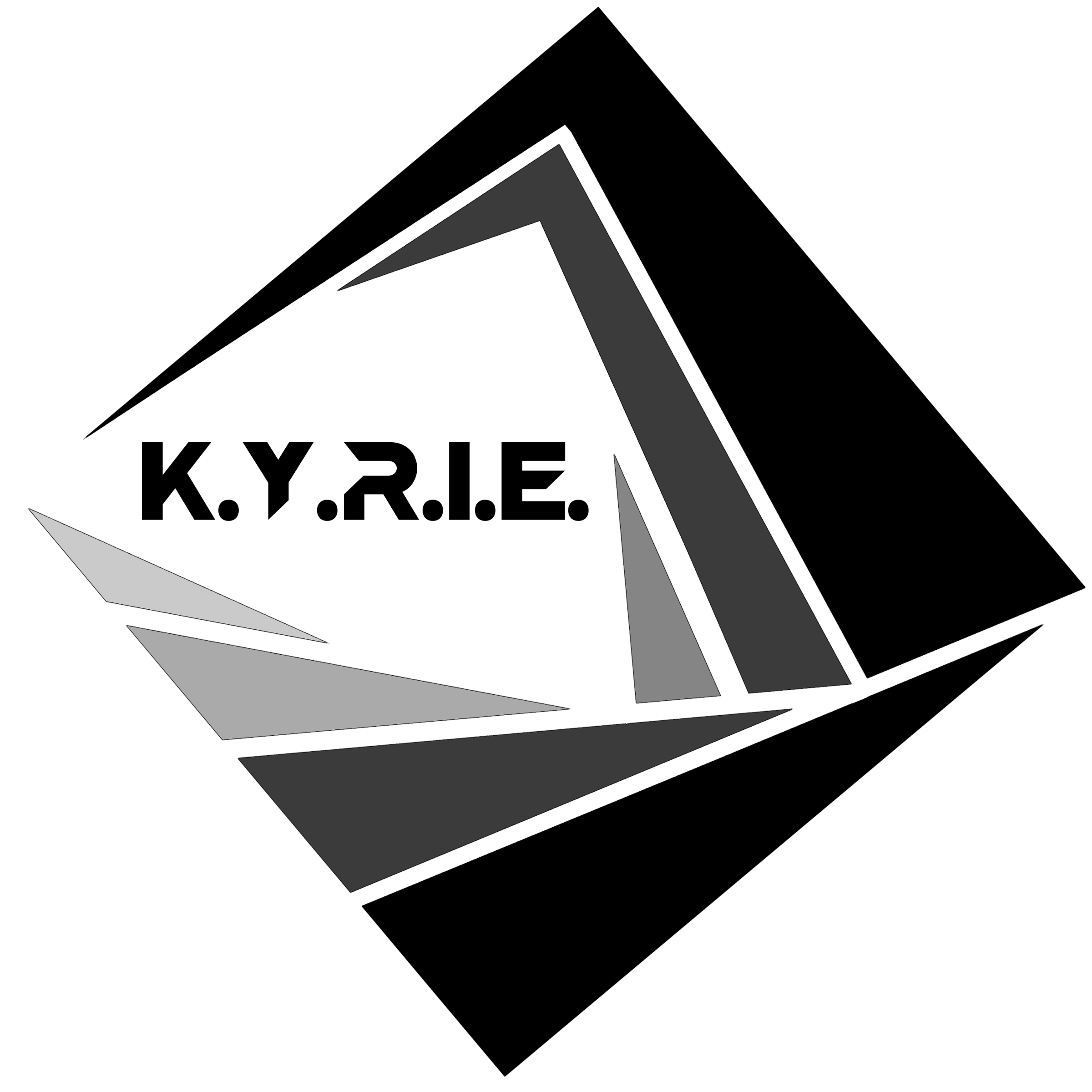やさしいゆめ
全てが奪われたような気がした。
立場も、愛も、目標も。自分を唯一動かしていた怒りや憎しみでさえも。
けれどそれはぜんぶぜんぶ、わるいゆめだったのかもしれない。
「――ん、んん?」
オフィスチェアを四つ並べただけの、寝具とは絶対呼んではいけない物体の上で目を覚ました。
ぼさついたウルフカットの髪をいじりながら、三峯 狼牙はのそのそと身体を起こす。
一日中灯りがつけっぱなしになった研究室は資料や機材で散らかっていて、壁面から浸蝕したそれらはいまや足場を欠きつつある。
その中を器用に歩いて、一人の女性が狼牙の顔を頭の側から覗き込んだ。
垂れ下がる髪を指で軽く押さえ、どこか揶揄うような表情をした、彼女――初富 葵。
「三峯くん、お疲れ様。もう何徹目? そろそろ死んじゃうんじゃない?」
「人間は寝なくても死なねえよ」
「ご飯もろくに食べてないでしょ」
「人間は飯食わなくても死なねえんだよ」
「ホントに死ぬやつでそれ言う人いるんだぁ」
葵は椅子に腰掛けると、狼牙の頭を掴んで引き戻した。
寝具とは呼べないと言ったばかりだが、キャスターつきの椅子の上でそんなことをされれば当然バランスを崩す。
為す術無く倒れ込んだ狼牙の頭を受け止めたのは、柔らかい感覚だった。
使い過ぎてつぶれかけた椅子のクッションでは断じてない、暖かくて、優しい感覚。
それが葵の膝なのだと気付いて咄嗟に起き上がろうとする狼牙の目元を、彼女の手がそっと抑えた。
「悪い夢でも、見たんでしょ」
暗く、暖かく、まどろむその甘さに、こわばっていた狼牙の身体から徐々に力が抜けていった。しぼむ風船のような気分なのに、けれどそれがどうにも、悪くない。
「……なんで、そう思うんだよ」
「うなされてたもん。また何かやらかした? 三峯くんってすぐ周りに流されちゃうからねえ」
「いつ俺が流されたんだよ。俺がトップに君臨することはあっても有象無象に染まるなんてことがあるわけが――」
「そーゆーとこだぞー」
声がすこしだけ近づいた。覆われた目からは見えないが、彼女が自分の顔を覗き込んでいるのがわかる。
「誰と比べなくたっていいんだよ。三峯くんは三峯くんなんだから。ちゃんと私は知ってるよ」
胸の奥に溶け込んで、身体をそのままどろどろにしてしまいそうな言葉に、狼牙は一度歯を食いしばった。
「……葵。手、どけてくれ」
「明るいと寝づらくない?」
「いいからさ」
狼牙は葵の手を取って、すこしだけ持ち上げた。
入り込んだ寒色の光が彼女の指――それも左手の薬指に嵌まった指輪を反射させた。
「ハハ……」
葵の代わりに、自らの手で目元を覆う。
「なあ、俺はさ。この時間が好きだったんだよ。
巳笠に張り合って、お前がそれを笑って見てて。たまにジジイにどやされて。
あー、そういや共同研究なんかしたこともあったよな。方向性でモメて解散してよ、バンドじゃねーんだからってまたジジイに怒られたよな。
俺はさ、青春とか知らねえし、好きな女もいなかったし、俺以外全員カスだと思って生きてきたけどさ。
この時間だけは、たぶん青春だったんだだよ。
俺が唯一、俺でいられた時間だったんだ。
だから、今なら分かる。
俺……お前の事、好きだったんだよ」
目元を覆う自分の手を、どけるわけにはいかない。
きっと相手にはバレバレなんだろうけれど。
「そっか」
葵は――巳笠 葵はそうとだけ言うと、狼牙の頭をそっと撫でた。
「オトナになったね。三峯くん」
「ああ、お前こそ……結婚おめでとう。お前のガキは、イイ奴だったぜ」
全てが奪われたような気がした。
立場も、愛も、目標も。自分を唯一動かしていた怒りや憎しみでさえも。
けれどそれはぜんぶぜんぶ、わるいゆめだったのかもしれない。
「いい夢を見せてくれて、ありがとよ」