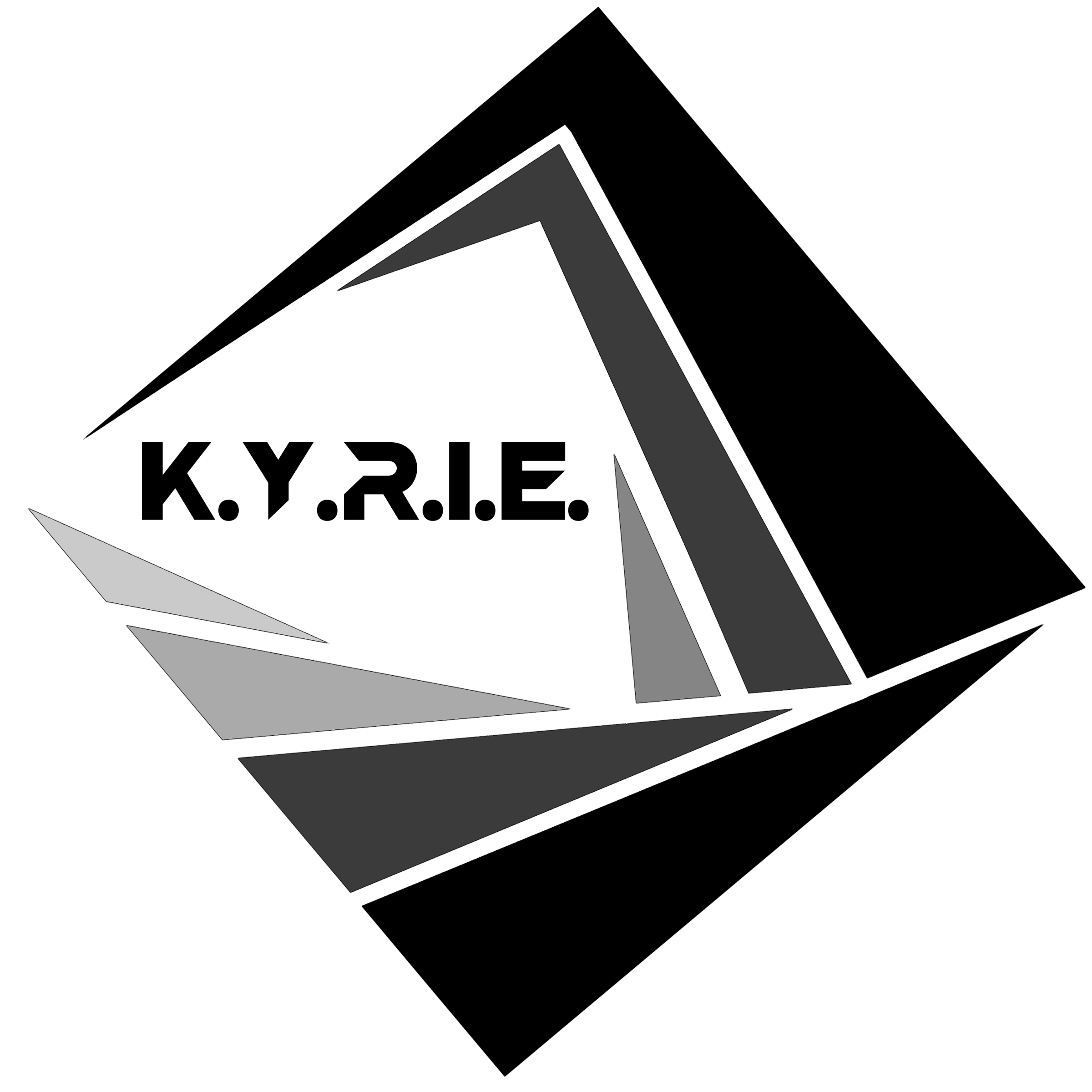シーズンテーマノベル『茜さす旅路』
乾いた風が吹き抜けた。青褪めた空は何時しかその色彩をも変えていく。
黒衣のように背へと張り付き伸びゆく影を踏む。子供の楽しげな声音は過ぎた報奨のようだった。
この街はかりそめの平穏を生きている。ただ、それを愛おしいと思うのだ。
人も、街も、動物たちも。何もかもが変わったという世界。
変わった後に生まれた者と、変わり果てた後にやってきた者。それから――変容の只中に居た者。
無数の者が交差し合えども、季節は変わることなく巡り行く。
出会いを経て、茂り鮮やかな陽射しを通り過ぎ、陰る陽光の傍に佇んで。
若々しく揺らいだ葉は気付けば赤く色付いた。廃屋へと絡んだ蔦はかさりと音を立て枯れ窶れて姿を変える。
また、秋がやってきた。
――艶やかな実りと共に、別れの気配を湛えながら。
商品概要:シーズンテーマノベル
| 商品 | 説明 |
|---|---|
対応商品一覧
発注可能クリエイター
|
基本価格 100RC~ |
景品
シーズンテーマノベル限定アイテム『Souvenirs de lune』
サンプルSS:『feels like fall』
登場NPC:春名 朔(r2n000031)、悠尋(r2n000083)
夕暮時に影が伸びた。靴先にぴったりと張付いて、忘れる事の出来ない記憶のように傍らに存在して居る。
青々と茂っていた緑化地帯の蔦の中にはそのかんばせを赤らめたものも存在して居た。
壁面を撫でればがさりと音を立てて落ちて行く。嘗て、やるせない程の喧騒に塗れたであろうこの場所に今は風の音しか残されてやいなかった。
マシロ市の内と外。何の気なしに平和と日常を与えてくれる街並みはおびただしいビルの群に己ら人間を埋没させて安堵を与えてくれていたのだろう。
外に出てみれば見果てぬ荒廃に自ら達の平穏などちっぽけであったと感じさせる。
偵察任務を終えてから春名 朔は肩を竦めた。感傷に浸る時間も無駄な程に急き立てられて生きている。
やれやれと肩を竦めて市内へと続く通路へと一歩踏み出した時、ポケットの中で父が愛用していたオイルライターがかちんと音を立てた。
今日も、得られたものは何も無かった。マシロ市は狭い。いいや、世界は驚かんばかりに広いと言うべきか。
砂漠の中で一粒ダイヤを見付けるような心地なのだ。早々易くは諦めやしないが――どうにも参るのは確か。
この通路は、マシロ市外に出るために能力者達が幾人も通った場所だ。今は伽藍堂としており、人の気配の一つも無い。
K.Y.R.I.E.はここから能力者を死地へと送り出し、新天地を求めるように長く苦しい航海を求めてきたのだ。
思い耽るのも莫迦らしい。ほら、帰ってさっさと仕事を片付けてしまわねば――
「やあ、朔」
「……こんな所で何を?」
耳に覚えのある声音だった。やはり、と言った様子で朔はまじまじと彼を見た。落ちた影がそのかんばせを隠してしまっていた。
誰そ彼は知った声だけで生者を誘うと聞いた事がある。さて、目の前の男が怪談の一つだったならば笑い飛ばしてやりたいものだ。
おのれがあの男を信用しているとでも囁かれているかのようだからだ。信を置く相手は選んだ方が良いだろうと自嘲してから朔は「悠尋さん」と名を呼んだ。顔を上げた男のかんばせに張付いていたのは何時も通りの笑みだった。
「何をって……迎えに来たんだ。迷子になってやしないかと少し心配しただけだよ」
「迷子になるような年齢ではないですよ。
――それに、帰らない事だって辺り前だ。そういう仕事でしょう」
「それでも、心配をする子達が居るからね」
「そうですか。……ほら、下らない事を言わずに帰りましょう。夜が来る」
かつん、と靴音が響く。反響し、風が浚って行く。まるで匙で掬うような簡単な仕草で悠尋は朔の手首を掴んだ。
眉を寄せてあからさまな不快感を表した青年が振り返る。その表情をしている内は元気なのだろうと唇の端で笑ってから、そっとおとがいを掴み上げた。
思わず息を呑んでから「何を」と問うた青年は幾分も幼く見えた。そうしてから漸くその目が悠尋を見たのだ。
「悠尋さん」
能力者達には余り聞かせぬ不機嫌な声音だ。らしくない幼い子供の様な拗ねた気配を孕んでいる。
古い馴染みには時折斯うした顔を見せるが、そうしている方が彼らしいと言うのは敢て口にはしなかった。
「……頭に赤らんだ葉が。取ってあげようか。随分と秋らしく粧ったんだね、朔」
「それは、どうも。こんな事をしなくても、言って下されば自分で取れます」
「ここまで迎えに来たのだから、君が驚く顔のひとつやふたつ、見たってバチはあたらないだろう?」
「頼んでなんてないです。見なくて結構です」
どこか尖った言葉遣いで彼はじらりと睨め付けた。それから、そっと掴み上げていた指先を解くように朔がその腕を降ろさせる。
「行きますよ」とだけ言ってからそのまま背を向けて階段を降りていく彼を悠尋は見送った。
その背中に張付いた寂寞は、きっと離れる事は無い。まるで影のように後悔がさんざめいて嗤っている。
終末論者と呼ばれた存在は、確かに生きた人なのだ。マシロ市で生きる遍く人々と同じような、当然の生を謳歌する者達だ。
彼等によって齎された父の不条理な死を追いかけて生きているのは嘸や苦しい事だろう。欠けたパズルのピースを探す様にして過ごす様は心ここにあらずだ。
「――可哀想な朔」
迷子に何てなりやしないと言いながら、迷子のような顔をして立っていたのは何処の誰なのか。
そんな事は口にせず、悠尋は彼の背中を追掛けた。
マシロ市は平穏と日常の象徴だ。その中に戻ったならば、寂しい風の一つも吹きや為ず、ただ、何時も通りが待っている。