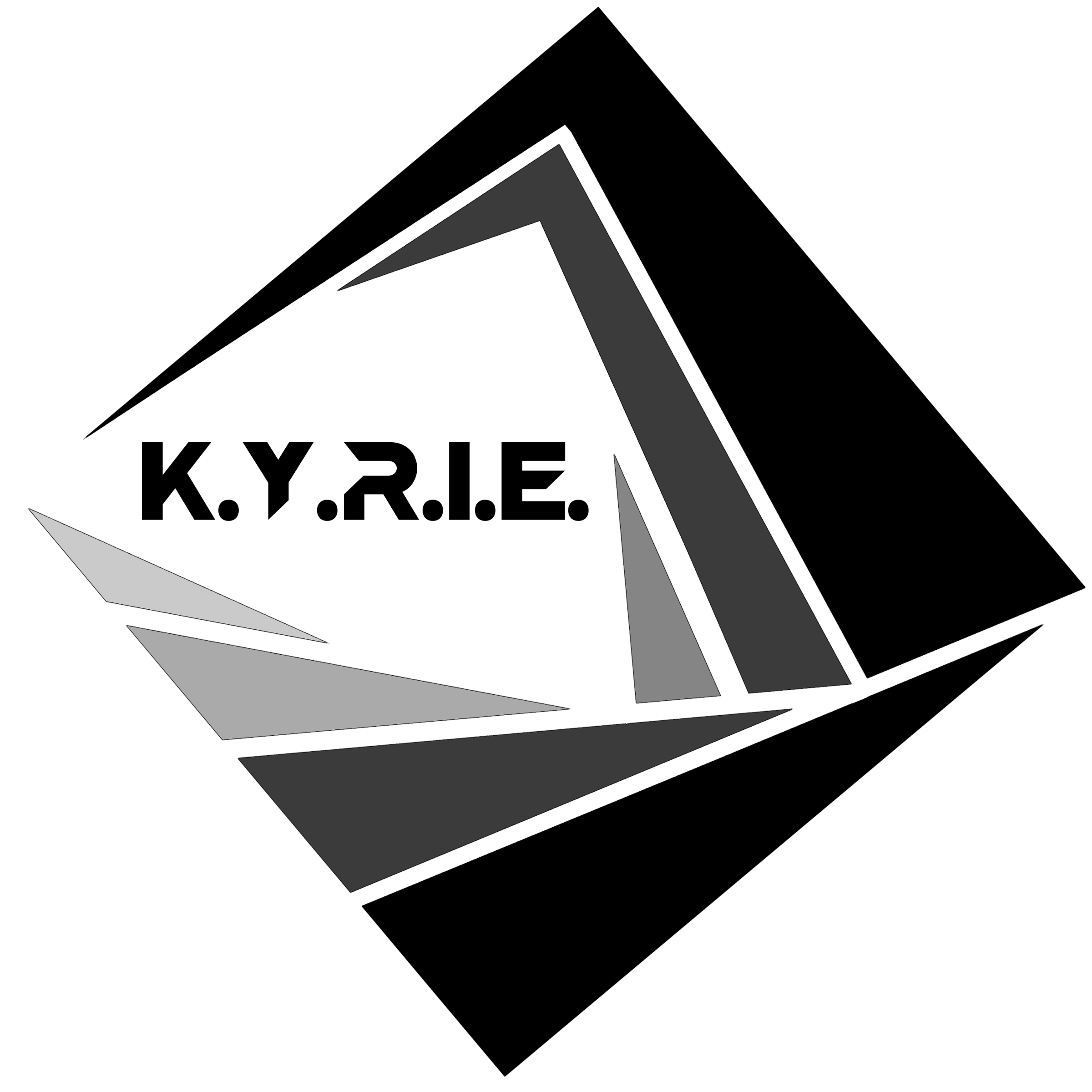夢見る鋼、銘無き刃
いまはむかし。月の出るある夜更けのこと。
赤い橋の手すりの上に、一人の女が腰掛けていた。
「川へ落ちるぞ」
憮然となげつけられた言葉に、女は白い狐尾をくねらせる。
振り向けば、和服姿の男が腕を組んで立っていた。
女は表情を緩め、白銀の髪の間からたてた狐耳をぴこぴこと動かしてみせる。
「わしが濡れたら困るかえ? それとも、わしがそんなに大事かの」
女が袖を口元にあててくすくすと笑えば、声をかけた男はそれこそ憮然とした様子で息をついた。
「冷えて病にでもかかれば面倒なだけだ。これからお前を振るわねばならんというのに」
「おお。なんと非常な。所詮そなたはわしの身体が目当てなのじゃな……」
よよよと袖を目元にもっていって見せると、男は更に憮然とした顔を深めていく。
「いやらしい言い方をするな」
隠した袖の下でこらえきれずに笑い声をあげ、女は橋の外側へと向き直る。
川のほうへとなげだした足を、ゆらゆらと交互に振ってみた。
つま先にひっかかった赤い靴の先。
月光が水面にゆれて、さらさらと穏やかなせせらぎを鳴らしている。
遠くでは虫の声が混じり、空気はどこまでも涼やかだ。
女が鼻歌をうたってみるが、歌詞を覚えていないのかほとんどふふふんと誤魔化している。男はその様子をただ黙って後ろから見つめ、組んだ腕をそのままにしていた。
「あ~あ……早くいくさにならんかのう」
2053年。鎌倉、仙泰宮。
座敷に箱が置かれている。
黒い漆塗りに彫金細工の施された細長い箱は紐解かれ、蓋が外れたままその側面にたてかけられていた。
中には赤い布が敷かれ、細長い何かが、具体的には日本刀が入っていそうな、箱である。
しかし箱の中身は空っぽで、本来そこに入っていたであろうものは……その傍らに寝そべった女の胸に抱かれていた。
白拍子を切り抜いたような服装は乱れ、袖や裾がだらしなく広がっている。
ころんと寝返りをうてば、女の白い狐尾が畳を撫でた。
「御刀様、御刀様、起きて下さいな」
ふすまが開き、入ってきた巫女装束の者が畳に膝をつく。
女はわざとらしくそれに背を向けて寝返りをうちなおした。
「むにゃむにゃ」
「寝ている人はむにゃむにゃとは言いません」
「あと5分」
「どこで覚えたんですかそんな言葉」
女は刀を抱いたまま、自らの髪からのぞいた白い狐耳をくしくしと撫で、半目を開いて上半身だけをわずかに起こす。
「なんじゃ全くう。折角いい夢を見ておったのに」
「夢なんて見るんですね、あなたでも」
「いや、見ぬよ。人間じゃあるまいしのう」
いい加減寝たふり(?)も飽きたのだろうか。女はやっと身体を起こし、抱えていた刀を強く胸元へと寄せる。豊かな胸が潰れ服の隙間からはみ出るのを、巫女は目をそらしてやりすごした。
「……見ないものなんじゃが、何故じゃろうのう。昨晩はいい夢を見た。存分に殺し合って、傷つけ合って。久しぶりじゃったのう」
頬に朱をさし、唇に指を当てる。
身体に溜まった熱をさますように漏らした吐息が彼女の指を湿らせる。
まるで恋をする乙女のような眼差しは、窓の外へと向けられていた。
やっと視線を戻した巫女がため息混じりに首を振った。
「何でもいいですけれど。お役目はきちんとこなして下さいね。さしあたって今日は――」
「ああ分かっておる、分かっておる」
女は憮然と手を振って、窓の外へ向けた視線を遠くした。
夢で出会った、あなたを想う。
「あ~あ……早くいくさにならんかのう」