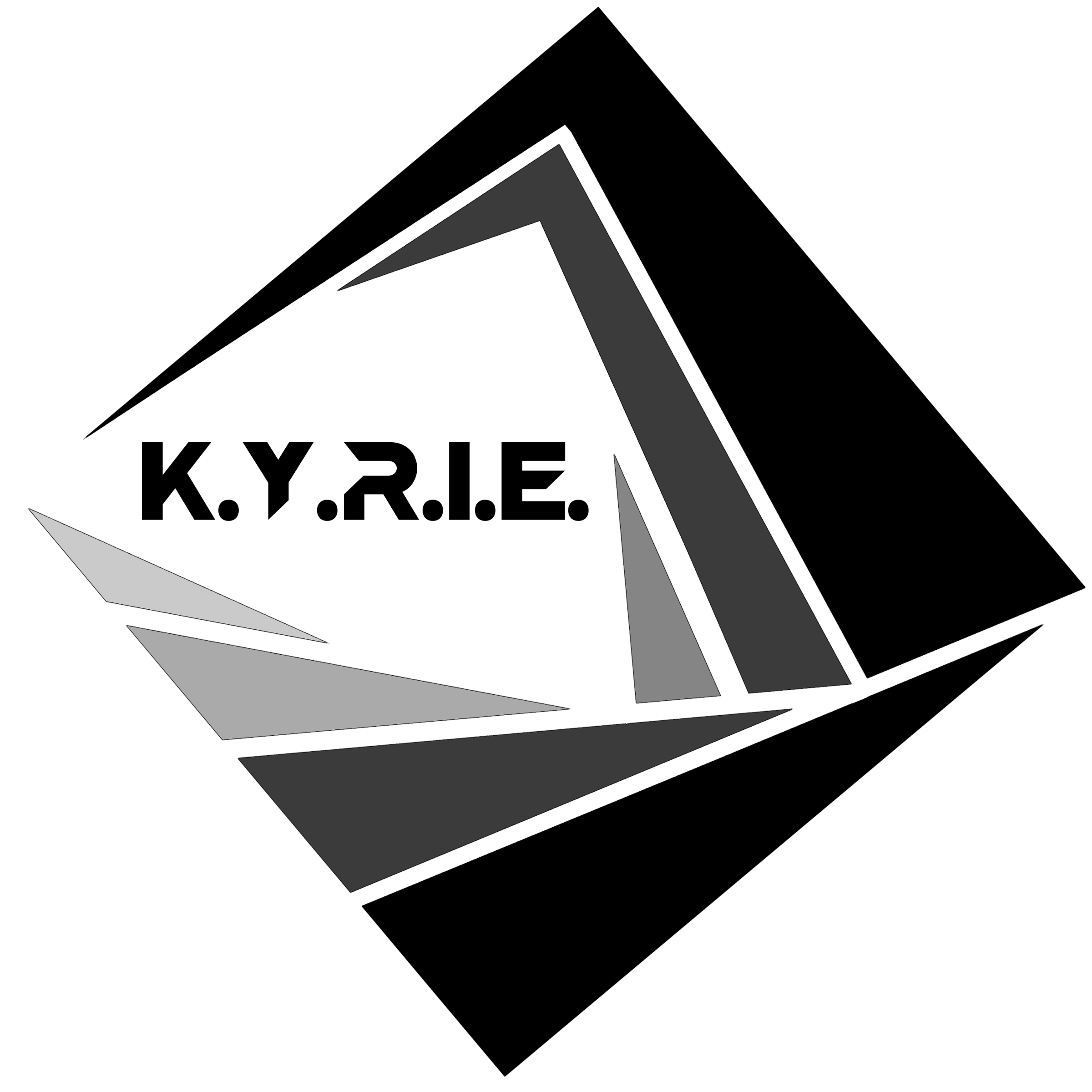天廻御神爾
今日こそ『言わなければいけないこと』がある。
宮羽 恋宵は元気よく、ふんすと拳を握った。
そして梅花の香と、やわらかな春風に誘われるように走り出す。
ここ鎌倉は退屈だ。
お役目とかいう古臭い風習を押し付けられ、恋宵は毎日それをこなした。
おかしな『からくり仕掛け』を動かすお仕事だ。まるで旧時代にあったらしいと聞く回転寿司なる飲食店の地下で、なにかこう河童が回しているような棒だとか。あるいはハムスターが走っているようなものだとか。
奴隷かなにかがさせられているような、格好悪い、かわいくない仕事。
「河童女🥒はほんと嫌、ハムスター女🛞が最低妥協ラインかな☆」
天廻御神爾とかいう、良く分からない名前の古臭い儀式。
心から気に入らなかった。
なんのためにやっているのかも、まったく分からないのだから。
「でもね――」
――そんなものは今日、終わらせる!
これまで恋宵は良い子にしていた。
言いつけを守ったてきた。
雨の日も風の日も雪の日も、毎日欠かさずに。
十二年も。
だからこそ不満だってある。
外が見たい。マシロ市に行ってみたい。
刻陽学園で勉強がしてみたい。
買い物とか、お出かけとか、スポーツとか。
何よりも、あの人たちともっともっと仲良くなりたい。
友達になって、それから。
そんな本でしか知らないような、あれこれ全部を体験してみたい。
――だってあの人は刻陽学園に行けるって言ったよ。
それにあの子も天使になるぐらいなら死んだ方がましっていってた。
ほかにもあの人も言ったんだ。それは青春だって。
あの子だって、もっとたくさんお互いを知って。
そしたら本当の友達になれるかもって――。
だから今日こそ、しっかりと尋ねるのだ。
このお役目は、いつ終わるのだろうかと。
そしていつ、マシロ市に行けるのかと。
相手は先代様でもいい。黄蓮様でも。
とにかく話を聞いてもらうのだ。
「これは絶対の決意だから、私は頑張っちゃうのです。おー☆」
――私、春から高校生になる🌸💯
こうなれば居ても立っても居られない。
速足に渡り廊下を通り、いつも誰かいる場所へと足を運ぶ。
心が躍っていた。
晴れやかだった。
何物にも負ける気がしない。
「黄蓮様!」
返事はない。
「先代様!」
やはり誰も居ない。
今日に限ってこんなこと、なぜ誰も居ないのか。
でもめげない。頑張る。
「だって今日の私は無敵だから!」
約束をしたのだ。
マシロ市に行くと。
あの人たちと――K.Y.R.I.E.の能力者のみんなと友達になるのだと。
そのためなら、なんだって出来る。
絶対にお願いを聞いてもらう。
それが今日だ。
「私は変わる、私は変われる、変わるんだ!」
――たぶんきっと今日のために頑張ってきたんだから!
部屋をきょろきょろしていると、ふと気づいた。
掛け軸が風に揺れている。
その向こうに、何か通路が開いていた。
「なんだろー?」
階段がある。
踊るような足取りで、恋宵は降りて行った。
壁に埋まるように、からくり仕掛けが見える。
どうやら地上と地下へ通じているらしい。
「あーこれ、お役目のかな?」
あのからくり仕掛けへ接続されているのが分かる。
好奇心にかられた恋宵は、そのまま地下へとおりていった。
「なんだろこれ、え」
生臭い鉄のにおいに足がすくんだ。
「なに」
べっとりと血の跡があった。
そして地下へ通じる仕掛けの先には、人がつながれている。
「うそ、そんなわけない、こんなの知らない」
仕掛けは明らかに、人体を傷つける構造をしていた。
苦痛を与えることに特化した作りをしていた。
当然のように、その人は、血を流して意識を失っている。
「私じゃない、私こんなことしてない、うそ、こんなの絶対に嘘」
助けようとすら思えなかった。
ただ、へたり込んだ。
体中が震えて動かなかったから。
毎日のお役目は拷問と殺害だったと知ったから。
十二年間、毎日、欠かさずに。
恋宵は誰かを傷つけ、殺し――
――齢、若干十五にして、干支を見事一巡り。
頭上から響く声がした。
「……せつ?」
よく知っている。せつの声だ。
けれど身体の震えが止まらない。
声もだ。それに視界だってひどい貧血の時みたいで。
「それほどお役目に長けた恋宵嬢にあらせられますれば。
いかほどの者等に六道輪廻を歩ませたか、最早数えるのも億劫でありましょうが。
始まりはお母上にござりましたな」
階段を下る足音と共に、せつの声が近づいてくる。
「何、なんのこと、意味わかんない、知らない」
「まさかまさか、覚えてすらおられぬとは」
せつの音は、あきれ果てたものだった。
「鎌倉にそんなにたくさんの人が居るはずない」
「お一人様お一人様ずつを、長く丁寧に苦しめることができましたな」
「せつのうそつき、そんなわけない、私じゃない」
「よもやこれを目にして天へ昇れませぬとは。
げにあさましきや、その性根、犬畜生にも劣りましょう」
「何なの、ばかにしてるのだけはわかるけど!」
「ご自身が成して来たお役目を知ってなお、怒り、否認、自己弁護。
愛も、情も、罪悪すらも浮かびませぬか。
まさかそれで、いっぱしに『人のつもり』とでも」
せつが何を言っているのか、理解できなかった。
(私は良い子、そんなことするわけない)
「いやはや、このからくりを考え産み出した宮羽 妃卯のよう」
それは話に聞いた、亡き母の名だった。
母のことなど、幼すぎて覚えていない。
最初のお役目だって、子供のころすぎてすっかり忘れている。
――天廻御神爾。
それは『生者のまま地獄へ堕ちることで三毒を御祓い天へ昇る』とされる儀式。
生きたまま六道輪廻を駆け羽化告解へと至るべし。
様々な教義をぐだぐだに合わせたような、まるでマトモじゃない教え。
堕天使が天使になればそれでよい。
はじめは『ただ人』から至れぬかとも試されたが、いずれもみな死んだ。
だがなれぬのならば、それはそれでよい。
その命はおおいなるものへの供物となろう。
これこそが、恋宵の母である妃卯が残した発明品であった。
「しかしまた、初めての役目で、実の母を手にかけてすら」
せつの嘲笑は悪意を含み余りあるものだった。
曰く、初めての犠牲者は、この拷問器具を生み出した恋宵の母自身であったという。
それが恋宵の『初めてのお役目』だったのだという。
死んだのか。それとも天使となったのか。そのどちらかということ。
知らない。そんなの聞いてない。
いやだ。私のせいじゃない。
鎌倉は綺麗なだけではないと、勘づいていたはずなのに。
でも、だって。お母さんのことなんて、顔も覚えていないのに。
また見ないふりをした。
また責任転嫁をした。
恋宵は自身のそれをクズの所業だと思った。
違う。
違う違う違う違う違う!
ぜったいちがう!
「私、良い子にしてた、してたし、言うことも聞いたし、休まなかった」
わたしはなにもしてないわたしはしらないわたしは
わたしはわたしは――
「良い子ですとな、人の情もない、天使のなりそこないが。よもやよもや、どの口で」
せつが嘲嗤う。
「左様に名乗らば、せめて御使いとして、新たな役目を果たしますよう」
良い子なら出来るのだと。
さもなくば、今度は恋宵がお役目の次なる贄となる他にないから。
「それこそが善行なれば、必ず報われまする」