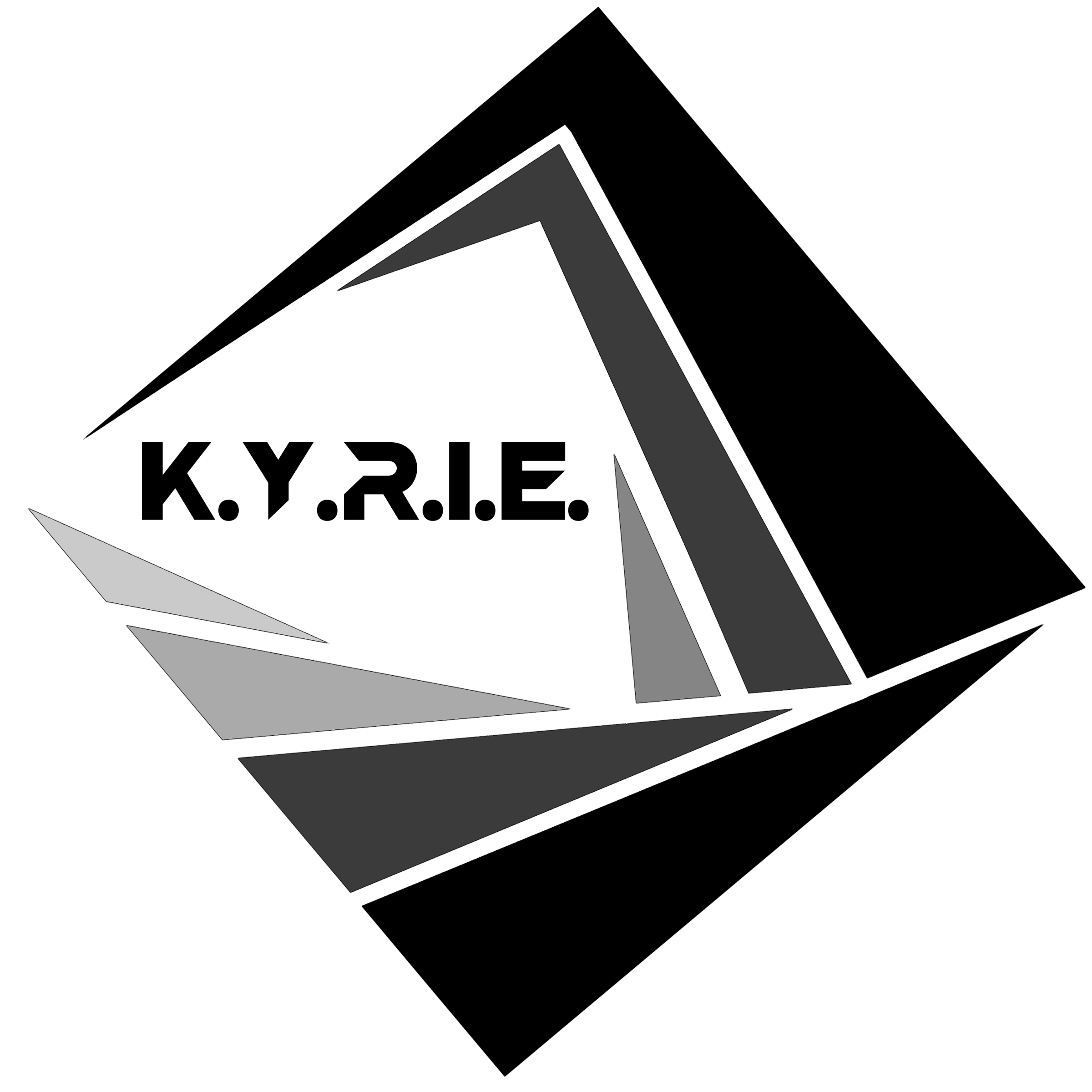誰そ彼に呼ぶ
息が詰る。この地でただ、只管に命を繋いでいるだけだ。
そもそも、自身が活かされていたのはこの身に流れる血が由縁。
血の濃度が高かったことで活かされているだけに過ぎず、無用になれば打ち棄てられる身の上であっただろう。
息が詰る。当り前だ。このような場所で人間が長く生きられるわけもなかろうよ。
比売神の加護は疾うに弱まって仕舞ったか。名を改め、姿を改め、信仰が代替わりすれば朽ちた社に神は居着かぬ。
あの様な冒涜、許されてなるものか。
冥冥の裡に続けられてきた呪法であるというならば適切に葬らねばならなかったのだ。
阻んだのは誰ぞであったのかは今になれば一目瞭然であったが、それを直ぐにでも見抜けなかったのは未熟だったからだ。
「せをり」
名を呼ばれてから古月 せをり(r2n000108)はのろのろと顔を上げた。
酷く窶れたかんばせに深く刻まれた隈と、苦悩の表情は暫しの間は消えることはないだろう。
「……しーちゃんは、うまいこと動かはったの」
「そう、でしょうね。……けれど、少し後手に回ったかもしれない。あいつの動きが速かった」
六華の悔しげな表情を眺めてからせをりは何処か疲れたような笑みを浮かべた。
しーちゃん――佐伯 シルビアはここ鎌倉によく馴染んでいた。六華とてそうだ。何方も自らの出自を隠し本来の目的を果たして来た。
一方はこの地で嘗てより用いられてきた呪法の確認を。もう一方は本来の鎌倉の統治者としての補佐を。
そう、せをりの目の前に立っている娘は血の道で繋がっている。親類と呼ぶにはどうにも他人行儀ではあるのだが……神祇院にその名を連ねる家系同士、血縁関係となったのは血を与して結束を高めるという意味合いがあったのだろう。
その末に斯うして二人は共謀者となった。いや、シルビアも入れるならば三名か。
「天地躯を封じるのは、もう間に合わない」
せをりは呟いた。六華とてそれは理解している。シルビアもよく分かって居るだろう。
「でも、今のアレは――『産土神・天地躯』はこの結界の中にある。
本来の結界より徐々に、徐々にこの領域は狭まって、もう宮の周辺一帯しか包めとらん。
……けれど、それでも、暫くの間はあれを封じている事が出来た。時間稼ぎにはなった、やろう?」
「せをり……もう無理よ」
「分ってる。うちにももう時間が無い。
あいつはうちを呼びに来るよ。もう、直に……そうしたら、うちに待ち受けるのは終わりしかない」
ふ、と笑みを浮かべるせをりに六華が唇を噛んだ。
現在の鎌倉の民は信仰をしている。おおいなるものはこの地を救い給う神であり仇敵なる天使をも屠ると信じられている。
嘗てとは違った信仰の形だ。何故か、それは「伝え方の問題」である。
おおいなるものを神として伝えているだけだ。
天地躯は永遠の安寧を地の人間へと与える。
習合の果ての果て、地縁によってそれは守護を与えてくれるというのは耳障りの良い言葉となっただろう。
その成り立ちが何処であるかも分からない。六華はそれを悔むことしか出来まい。せをりとて、そうだ。
神祇院はこの呪物の監督を行って居なかった。
つまり、この地に秘匿された術式は意味を転じて掘り返され悪習であることをも忘れられて作り上げられたのだ。
呪物に他ならぬものではあるが、永劫の避難所を得るが為に術式は用いられ――それは由比ヶ浜より続く鍾乳洞の地下へと眠ることとなった。
「どうするの」
六華は問うた。せをりは小さく笑みを深める。
「うちの結界は天に、やつの結界は地に。
うちの結界は天より覆い、天地躯の――おおいなるものを封ずるためにある。
やつの結界は地より掬い、命全てを天地躯へと運ぶ為にあった。
……時間がない。けれど、結界をこれ以上緩めたらあれが出て来てしまう。地の結界に抵抗するんも時間の問題や」
せをりは眉を顰めた。
この結界は鎌倉の民を護る為に存在したのではない。
本来は悪しき者を封じ込むが為のものだった。それを地脈を駆使したヤツの術式が掬い取らんとしている。
その衝突地点に僅かな綻びが出来た。天使達が外から入ってきて能力者はさぞや気を揉んだだろうが……。
だが、それこそ必要な場所だった。そこからシルビアの作戦が為にマシロ市に彼等を戻すくらいの時間はあるだろうか。
暮色蒼然の頃。
もうすぐ、宵の刻がやって来る。
――結界はさらに強まって、能力者を外には出さないだろう。
もうすぐなのだ。もうすぐ、天地躯も完成してしまう。
「せをり」
――せつが、そこに立っていた。
「逃げられてしまっては仕方ありませんな。そろそろ――」
せつが、仙泰がそう笑った。
「いつまで、少女の振りをしているん、狸じじい。
菊ちゃん揶揄って遊ぶんも、黄ちゃんを掌で転がすんも飽きが来たんか?
素知らぬふりは何時までも通らへん……ごっこ遊びはもう、おしまいやろう?」