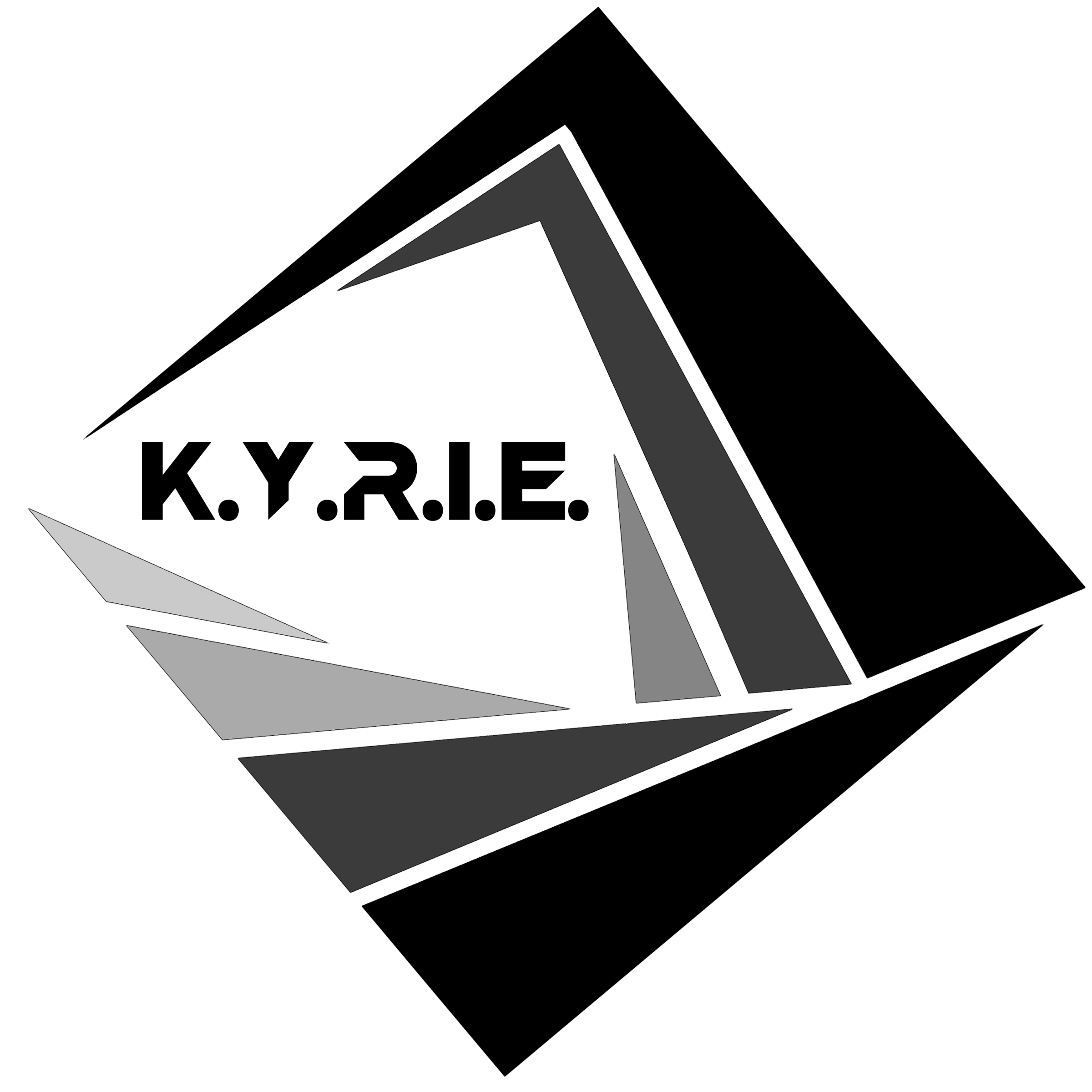ミステイク
「おう、坊主。相変わらずの顰め面だな」
楽園に君臨する10の熾天使――
至高と称される彼等の中でも際立って高いプライドを持つアレクシス・アハスヴェールにそんな無礼な呼びかけをする者は一人をおいて他に居ない。
「懲りずにまた賢しらな企てでもしておるのか。大概に暇な天使だ、お主も」
「そういう呼び方はするな、と前にも言った筈ですが?」
同時にかけられた声にゆっくりと振り返ったアレクシスの表情に憤怒の色が浮かばぬケースも一つの他には無く、従ってその呼びかけは非常に稀有なる特定個人からのものである事を示している。
「バルタザール。どうして貴方の言行はそう品を欠き続けるのです。
人物にはその人物なりの責任がある。貴方も至天の一角。相応の礼節を身に着けるのは必要な事だと思いますよ」
「回りくどい男だのう」とぼやいたバルタザールにアレクシスは小さな嘆息を吐き出して諦念に満ちた表情を作っていた。
言葉は咎める調子だが、その声色は余り真剣な雰囲気を帯びてはいない。
呼びかけも然り、この苦言も然り。やり取りは形式めいていて、それはアレクシスとバルタザールの関係を良く表すものと言えるだろう。
水と油、全く毛色の違うこの二人は一見すれは最悪の相性にも思えるものだが、存外にその関係は悪くはない。
主な理由は粗野ながら豪放磊落にして比較的気のいいバルタザールが話せるタイプだからと言う所が大きいが、自らと他人を切り分け、徹底的に他者を侮り、利用しようとするアレクシスがこの男には然程そういう気質を見せないという理由も見逃せない部分ではある。
つまる所、非常に単純に説明してしまうならアレクシスはバルタザールに一目を置いている。
基本的に同格にさえそういう感情を持ち得ないアレクシスからすればそれは大変な例外と言う他は無い。
「暇人と言えば貴方の方はどうなのです。世界攻略は順調ですか?」
「愚問だなあ」
バルタザールはアレクシスの言う所の品の無い大欠伸をして頭をばりぼりと掻いていた。
「餓鬼の遣いなんぞ、御免被るわ。あんなもの儂が出るまでもない。下の連中が何とかするだろうて」
「言いますね。この楽園で。煩い小娘に聞かれでもしたら大いなる面倒が生じるでしょうに」
「楽園は不可侵、不戦なのだろ? 唯の小言が怖いならまずお主に話しかけたりもせんわ。
第一が割り当てが悪い。儂を動かしたいのなら相応しい好敵手でも配しておけという話だろう」
「成る程、道理ですね」
アレクシスは冗句めいたバルタザールに小さな笑みを零していた。
楽園の秩序は絶対だ。少なくとも不可侵を定めたのが父であるのなら、その走狗が大した理由も無くそれに違反する事はない。
バルタザールの怠惰等は彼の言う通り、馬耳東風の小言に収まる範囲の問題にしか成り得まい。
「それにしても好敵手、ですか」
「うん?」
思案の顔を見せたアレクシスはバルタザールに言葉を続けた。
「滅びを待つ被造物共に貴方の相手が務まるとは思いませんが、例えば。
……そうですね、例えば我々ならばどうでしょうか?」
まさにそれは試すような――実に危険な問いであった。
アレクシスの仄暗く鋭利な知性はその深い瞳に煌めき、水を向けられた赤毛の覇王へとその注意を注いでいる。
「やはり、くだらなく賢しらではないか」
「そういう性分なものでして。ええ、一度は聞いてみたいと思っていたのですよ。
実際の所、貴方が他のプレイヤーをどう評しているのか」
「話しかけなければ良かったかのう」とぼやいたバルタザールは暫し逡巡した後、「まあ良いか」とアレクシスの求めに応じる事にした。
「アレクサンドラは面倒だな。単純な武力だけではない厄介さが否めない。
マーカスは……うん、分かり易い。強いが足りん。若い故、時が過ぎれば超える事もあるかもな。
リズはまあ、子猫か。甘噛みに怒る王は小物過ぎる。双子も同じだ。誰が子供に本気になるものかよ。
順は前後したが、アマランスはまあまあ。そこそこ程度には楽しめそうだ」
余りに直截的なバルタザールの物言いに流石のアレクシスも苦笑した。
相手の様子に関わらずそれぞれの顔を思い浮かべるようにバルタザールは言葉を続けた。
「ディオンは危険な匂いがするのう。弱いが危険。だが、知っての通り儂はそういう相手を好かん。退屈だ。
それからミミか。うむ、アレが一番儂の眼鏡にかなう。怪物とやり合うのはどんな時代でも血が滾ろうというものよ」
「……では、私は?」
「お主については遠慮してやった心算なのだがな。小突けば飛ぶわ、うらなり如き。
……お主とてその程度の自覚はあるのだろう?」
「その発言をしたのが貴方以外ならばこの場で決闘を申し込む所ではありますがね」
「儂相手にそうする気骨があったなら、儂は大分お主を見直すがなあ」
冗句の応酬はやはり剣呑とした悪意を帯びていない。
バルタザールは唯の事実を述べただけであり、アレクシスも殊更にそれを否定してはいないのだ。
「最後はマリアテレサですが」
実を言えばアレクシスが聞きたかったのはその一点のみだ。
このゲイムを勝利する為の最大の障害が彼女である事は知れている。
少なくともアレクシス・アハスヴェールが戴冠に到るにはバルタザールとマリアテレサの決戦は必要不可欠なものだ。
そして、バルタザールが勝ち残るのが望ましい。
武力という意味ならば目の前の男も変わらない障害だが、やりやすさが全く違う。
「マリアテレサか――」
「ふむ」と一層の思案顔をしたバルタザールはこれまでのような即答をしなかった。
「……貴方が敵と見做す存在が此の世に居るとは思わなかったのですが?」
「儂を何だと思っておる」
「最強の熾天使だと思っておりますよ」
アレクシスの言葉にバルタザールは彼には珍しい苦笑いをした。
「それで?」
「分からん」
「……分からない?」
「うむ。やってみねば分からん。
まあ、少なくとも言える事は――あの女は怪物が可愛い猫に見える程度には規格外という事だ。
それが儂の戦斧を受け切れるものか、ひいてはこのゲイムを勝利するに値するものかどうかまでは分からんがな」