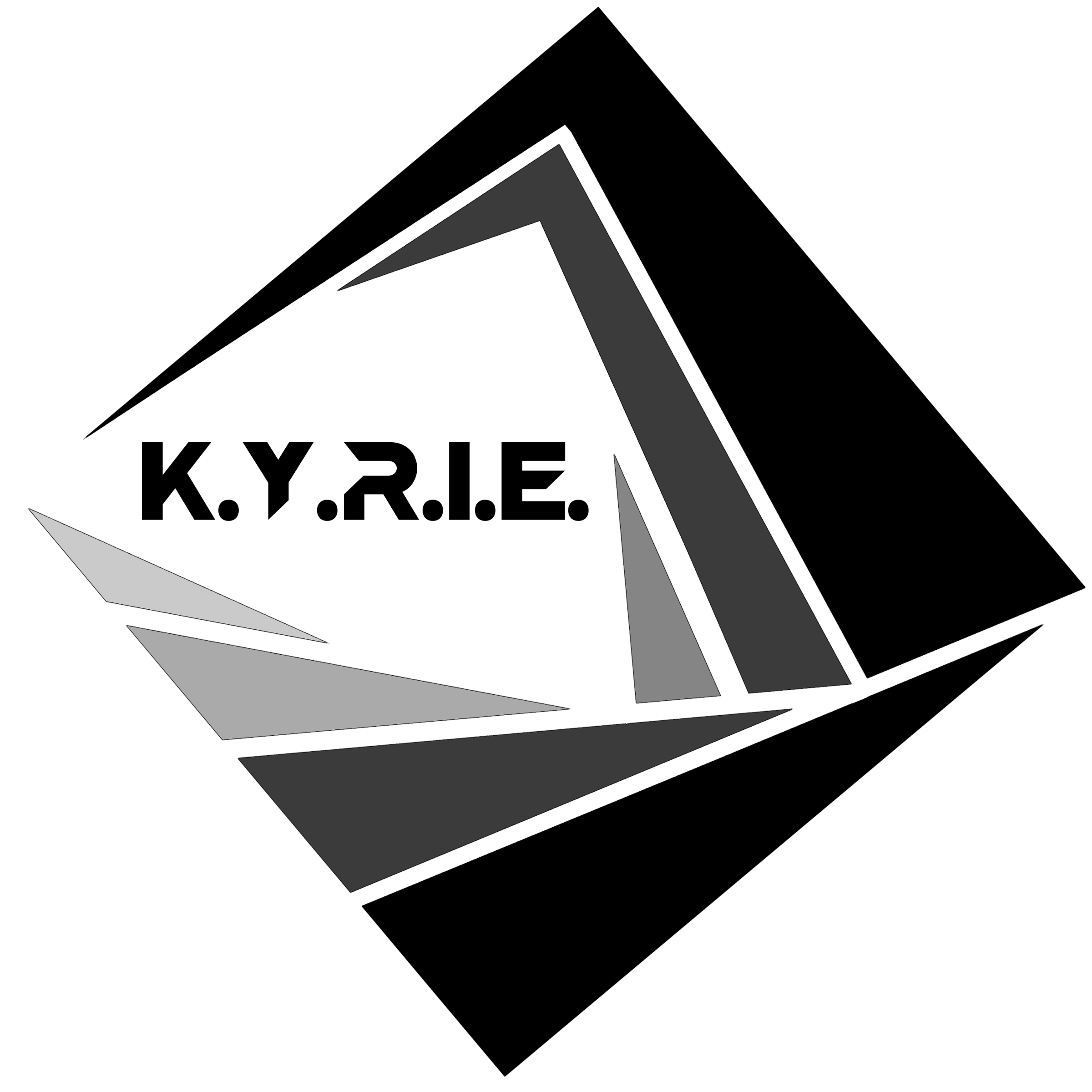終鐘と影法師
「――なるほど。仔細、承りました」
天に浮かぶ月が地を見据える。
薄き灯りに世界が照らされよう。だが、さて――
世の片隅には、その灯りにすら見つからぬように潜む者達が会談を果たしていた。
「ご快諾に感謝を。我が主の望みが果たされた後には、貴方達にもきっと主より祝福が齎される事でしょう」
「天つ使いの皆様の為に尽くせるのならば終鐘教会として実に誇らしい事ですわ。
わたくし達はその為に在るといっても過言ではないのですから――
ねぇ? カゲオミ」
「えぇ、えぇ、我らが光、指導者ヒルダ! しかし天使の方々から我々に接触頂けるとは。
終き鐘の音を聞いた同志らも羨む僥倖。予期せぬ幸福もあったものです!」
一人はヴァルトルーデ。アレクシス麾下の天使が一人であり、彼女の正面にいるは……人間だ。ヴァルトルーデとはまた異なる白き衣に身を包み、その胸に終鐘のしるしを持つ。片目を眼帯に包んでいる彼女の名は――ヒルダ。
終鐘教会なる終末論者組織を率いる長である。
以前マシロ市内で暗躍した数少ない組織であるグルガルタ……そう。すぐ傍にいる男、カゲオミが率いていた者達と繋がりのある存在だ。その身よりは妖艶なる雰囲気が揺蕩い、されど同時にどこか得体の知れなさを感じさせる気配もあろうか。
その唇より零れる言の葉の一つ一つは心に沁み込んでくるが如く。
只人と思い難き美しき肢体には思わず目を眩まされん――
これが終鐘の長。
人に背信し天に仕えんとする者だ。
「しかも、かのマシロの人間達に関する事でとは。思ったより早く縁が訪れたもので」
「――あら。カゲオミ、貴方お得意の潜入はもうお終いになったのかしら」
「ええ。少し前に色々とありまして。尤も……彼女は役立たずでしたがね。せめて幾人かだけでも道連れぐらいには……いや? 結局俺の身は無事なのですから目的は果たしてくれたと称えるべきでしょうか?」
「ふふ。瞳の奥に感情が渦巻いているのが見えるわよ。貴方は悪い子ね」
「恐れ入ります」
続け様、ややテンションの高いカゲオミが想起するのは妃野原いばらの件だ。
雷の領域とも称された地での戦い。元K.Y.R.I.E.の能力者であり、天使へと至ったいばらを様々な口八丁にて駆り立てたのがカゲオミである。その戦いの果てにいばらは散った訳だが――カゲオミは生きている。
あらゆる手から逃れヒルダの下まで帰還を果たしたのだ。
それが彼という男の性質である。
「ふふ……とにかくヴァルトルーデ様の仰る事は承知しましたわ。
間もなく彼らもこの近くまで来るはず。この地でこの子が準備を進めておきましょう。ヴァルトルーデ様の麾下の天使の方々も幾らか此方の方へ来ていただけるなら歓待の用意が必要で?」
「それは結構よ――あぁただ。此処に来る面々は、もしかすれば些か注意が必要な存在もいるかもしれないわ」
「……ほう? どういう事でしょう。それはマシロの面々という意でしょうか?」
「確かに人間の中にも煌めく才を持つ者はいるわね。
そちらの情報もターリルが収集してくれているし、無視は出来ない事も理解している。
けれどね、人間とは別。ある不本意な来訪者一派がいるのよ」
ヴァルトルーデが語るは、至上最悪に迷惑な主天使の配下たちの事である。
己が主の命であればこそ彼らとも歩調を合わせるが。はたして連中は一体どこまで信ずることが出来るか――彼らに比べれば眼前の人間達の方が、まだ御する事が出来るという意味で案ずれるものだ。
「あぁヴァルトルーデ様。なにやら悲しそうなお顔をされていますわね」
「何。我々にお任せください、何が起ころうとお役に立ってみせますとも」
「ふふ。カゲオミは良い子ね。なら――」
――役に立ったら、お姉ちゃんが重用してあげる。
男の耳元。吐息すら耳を掠める程の近くで囁かれる誘惑。
カゲオミの高揚は暴風の如く渦巻こうか。
あぁ強き者からのお言葉程ありがたいものはないのだから――!
「じゃあまた、ね」
「ええまた――機があらばお会いできる事を心よりお待ちしておりますわ」
瞬間。月の光が、雲に遮られよう。
瞼が閉じるかの如く一瞬の暗きが世を支配して……
直後に月の眼が開かれた時にはもう、ヴァルトルーデの姿はなかった。
天使。あぁなんと素晴らしき存在な事か。
ヒルデは既に消えながらも、先程までヴァルトルーデがいた場所を未だ見据え続け……
「カゲオミ。言われたとおりの備えはしておくように、ね」
「ええ勿論! ――しかしマシロはこちらの動きに気付くでしょうか?」
「勿論。希望のお柱がよるべにする程なのですもの」
「指導者はいつも、あの都市を評価なさる。それは些か妬けてしまいますね」
「ふふ……。一人と言えど、わたくしたちの足取りを掴もうとした警察官が居たではありませんか。
アレは死んでしまったけれど。わたくし、あの熱は忘れられませんわ。アレが居たから、希望のお柱もマシロに逃げてしまった。
その事実は覆せないのだもの。なら、受け入れるのみですわ。
……あの地に住む子達が愚かでないのだけは――確かでしょう」
でなくば。我々終鐘教会はもっと簡単に策謀を巡らす事が叶っていただろうから。
ヒルダは天を見る。そこには……静かなる月が浮かび続けていた。
あの月が如く、今日は静寂にして平穏だ。
あくまで今日という日に限っては――の話であるが。