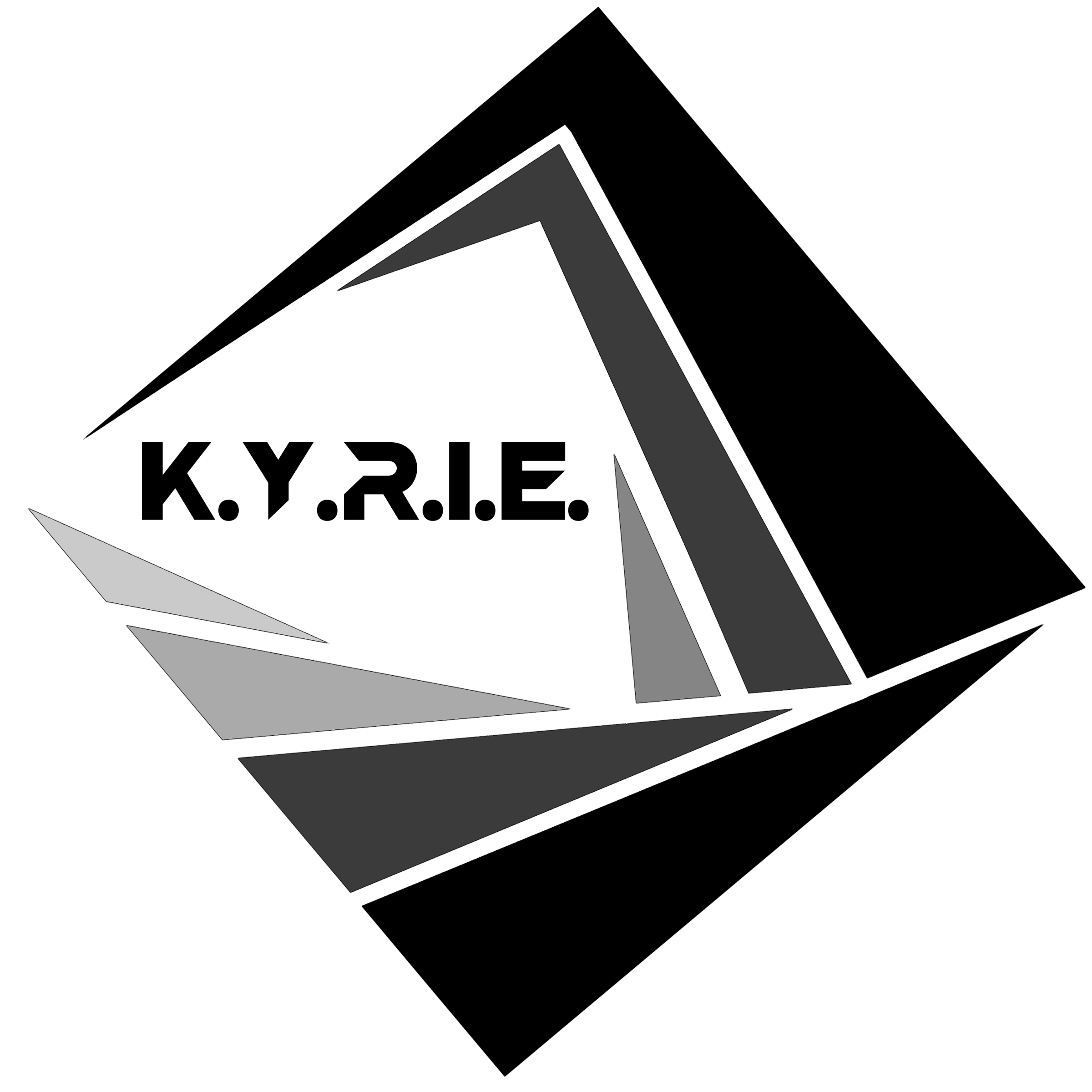現実と仮想の間
刻陽学園、保健室。
巨大構造ゆえにいくつか存在するそれの一つに、珍しい3人が顔を突き合わせていた。
吉瀬 瞳子(r2n000032)。蓮見 凪紗(r2n000013)。シェス・マ・フェリシエ(r2n000067)。
この三名である。
この三人に共通するところは何であろうか? 一つを上げるとするならば、その誰もが、レイヴンズへの健康活動に関与する者たちであることは確かだ。
瞳子は、K.Y.R.I.E.にてバイタルチェックを担当し、凪紗はこの保健室の主だ。シェスはアガルタ研究部の局長であるが、今回に関して言えば、それ故にこの場にいることも事実。
ということを考えれば、つまりこのメンバーが顔を合わせているとは、すなわちレイヴンズへ、何らかの肉体的影響を生じうる事態が発生した、ということでもある。
「まあ、別に大げさな話じゃないんだけどね」
と、瞳子が言う。
「ほら、ナナイっているでしょ?
『KPA(キリエ&パールコースト造兵廠)』のくそぼけ」
「たしか、技術開発部とは別で、兵器や一般システムの開発を行っているチームだよね。
それで、ナナイさんは、技術主任の方。ヴェテランの」
凪紗が言った。
「正式採用しているハンドガン、ナナイの基礎設計を行った方とも聞いてます。
優秀な方だとか」
「優秀? あれが?」
シェスは珍しく、露骨な感情を表して見せた。フレーメン反応にも似た微妙な表情だ。
「あれはもう、おかしいというんだ。紙一重というが、あんなに薄っぺらい紙一重を、私は初めて見たよ。裏が透けて見えるほどだ」
「あのナナイの人物評はどうでもいいんだけど。全員一致するところだろうし。満場一致で嫌いでしょ? あいつ」
瞳子が言った。
「問題は――これ。
題して、『現実的な没入型教育を実現するための仮想拡張学習キット』実験。
通称『V.A.L.K.Y.R.I.E.』システム」
そう言って、瞳子が冊子を放り投げた。それは、V.A.L.K.Y.R.I.E.システムの詳細を記された、イラつくほどにかわいらしいイラストの描かれた水色のパンフレットだった。
「新システムの、訓練キット……?」
「キットというか、KPAのワンフロアを利用した、半仮想・半現実の訓練システムだ。
アガルタの技術も随分提供させられた。サヴェージのデータもね。
多分、技術開発部にも協力を要請したんじゃないかな?」
「……大丈夫なのかな……」
凪紗が言った。提供されたパンフレットを、ぱらぱらとめくる。
「いえ、技術を信用していないわけではないのだけれど。
なかなか過激なことが書いてあるし……。
これ、現実空間での戦闘訓練も可能なんだよね?
より正確なデータの採取には、実武器が好ましい、とかも……ほら、ここに」
指さす。果たしてパンフレットには、イラつくほどにかわいいイラスト共に、過激な事実が記載されている。
つまり、これは実戦同等の訓練を行うことも可能であるが、それ故にレイヴンズに身体的ダメージが発生することもある、と、当然のように書いてあるわけだ。
「わかんないわね。
あのナナイからしたら、新しい訓練始めるから、あたしたちに、これまでより一層の、レイヴンズのバイタルチェックの実施とかデータ採取、メンタルケアとかを徹底しろ、ってことなんでしょ? ふざけてる」
と、瞳子は胸ポケットを探って、タバコを取り出――そうとしてやめた。禁煙だろう。さすがにここは。そうでなくても、凪紗に優しくたしなめられかねない。
「少し忙しくなるかもね、ってこと。
ついでにこれも、『いそがしくなるけどめーんご🌟』って言い訳でしょ。死ねばいいのに。
実際忙しくなるのあたしたちだってのに。腹立つ」
「ありえるな」
ふむん、とシェスが唸った。
「だが、実際、訓練システムの向上は、今の我々には垂涎のものともいえるよ。
私たちは、より外へ、より広範へ、進出しなければならないのならば。
多少のケガを織り込んでも、内部でより高度な訓練を行えるならば、それに越したことはない」
「……戦力の底上げ、という意味でも、だよね?
わかるん、だけど……」
「凪紗ちゃんは優しいからな」
シェスが笑った。
「まぁ、ナナイが何を目論んでいても、あたし達がやることは、今まで通り。
皆をケアしてあげることだけ。
死ぬほど腹立つし正直蹴り入れたいけど、まぁ、我慢するしかないわね」
「……」
凪紗は少しだけ困ったような顔で、うなづいた。心配、という点では、ここにいる三人の誰もが一致しているはずだ。
とはいえ、シェスの言う通り、戦力面の底上げ、という意味でも、高度な訓練システムの構築は必然と言える。
……結局のところ。皆の抱く不安や心配も、マシロ市という総体の抱える問題が表出したに過ぎないのであり、いつかは直面する、避けては通れない試練なのかもしれない。
さて、そんな期待と不安をない交ぜにした気持ちを抱く者たちをよそに、V.A.L.K.Y.R.I.E.実証実験の日は着実に迫っていた。