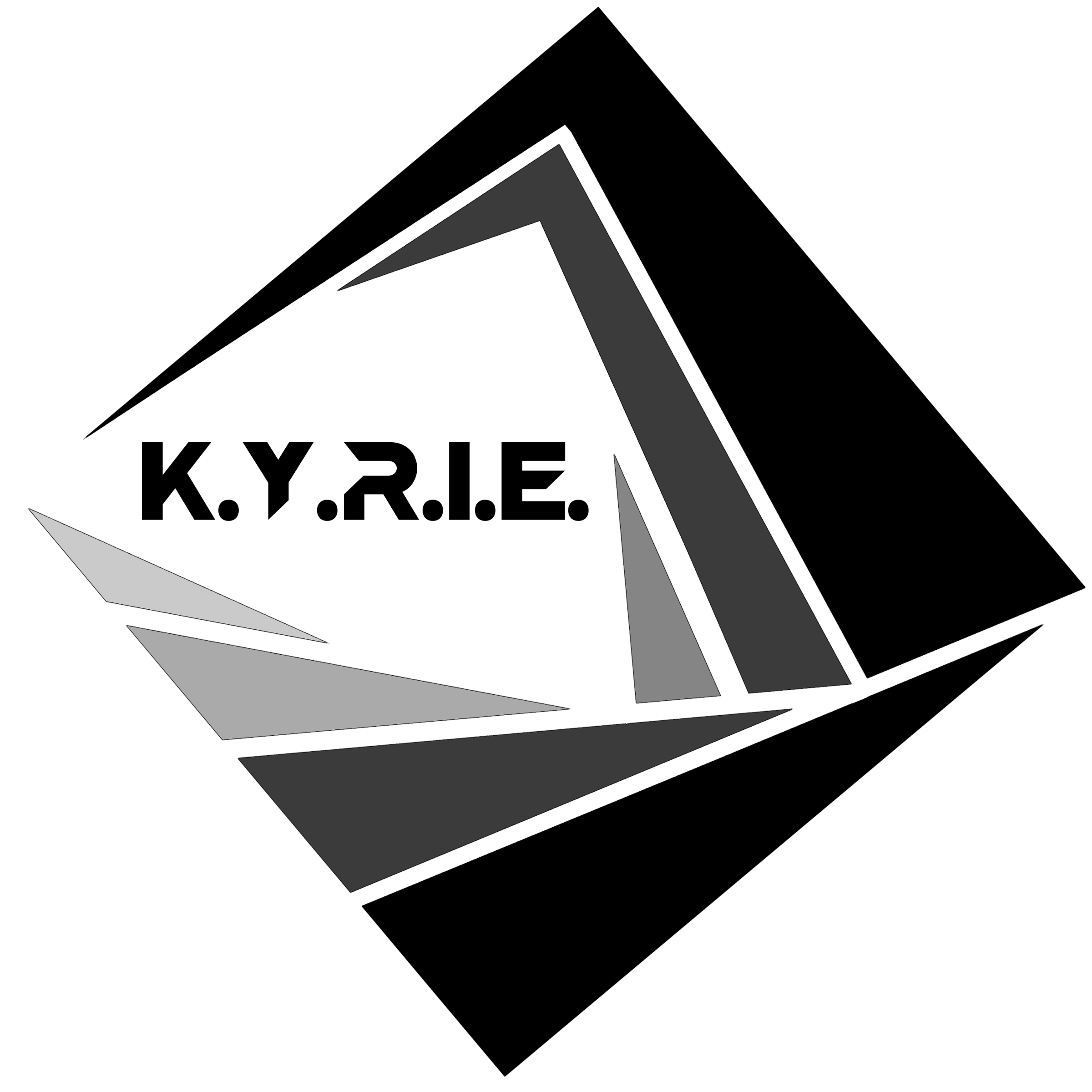アハスヴェールの影
「おや、珍しい時間にお会いしましたね」
一流の役者を気取る流麗な男はその内心を外面に僅かばかりも滲ませない。
「美しいマリアテレサ。一日等という人の尺度のその時間で、御身の姿を二度も拝見出来るとは。
これは中々の奇運。まるで何かを暗示するかのようなサプライズではありませんか」
その言葉の通り、宵闇に包まれた楽園に二人の熾天使が佇んでいる。
一人はこの楽園の実質の主人、即ち至高、マリアテレサ・グレイヴメアリー。
そしてもう一人はその彼女と会合を済ませた後の熾天使、アレクシス・アハスヴェールその人であった。
日中の会合は集合体として呼称するアーカディア・イレヴン達の集まりであったが、この時間は別物だ。
「性懲りもなく楽園をうろついているのは貴方の方でしょう、アレクシス。
僕からすればこの美しい夜の庭園を愛でる事も、然して珍しい出来事ではありませんからね」
「いや、中々手厳しい」
相も変わらず周囲を軽侮するかのような薄笑いを浮かべたアレクシスは、お互い様の女の辛辣な言葉にも頓着しない。
少なくともこの男はその内に燃え盛る黒い憎悪の炎を端正な顔に示すような愚は侵さない。
(マーカスのような単細胞と私は違う)
結局は最終的にどうするかが全てである。
現状を正しく認識、認定し。最も賢明に、最も確実な最適解を選び取る事。
神に与えられた最悪のチャンスに大願を捧げようと思うのなら、慎重は不可欠だ。
(だが、残された時間が然して多くないのは事実だ)
……同時にかなりの大胆も要るのが厄介である。
マーカスとフレアは同盟を結んでいるのだろうが、アレクシスに言わせればそんなものが焼け石に水なのは確定的に明らかだった。
ディオンも巨大な何かを企んでいるだろう。そしてミミは或る意味において決定的に重要である。
子供や中立派の連中は知らないが、少なくとも現状では決定的な何かが無ければ決して――は、無い。
「私の動機が同じではいけませんかね、マリアテレサ。
楽園は美しい。貴女だけが楽園を独り占めするのは些か卑怯だ。
ええ、分かっていますとも。貴女はアーカディア・ワンだ。
父なる奇跡に最も愛された個体である事は間違いありますまい。だが、それでもです」
まさに何よりも認め難い事実を呑み込まねばならない事がアレクシスにとっては最大の屈辱である。
故にその心中で激しさを増した黒を覆い隠すように彼の弁舌はより一層に滑らかさを増していた。
「アーカディア・イレヴンは等価と設定されているのだ。御身が何より敬愛する、他ならぬ父自身にね。
故に貴女には命令権は無い。そして貴女は父の意向を無碍にはしない筈です。正解ですよねえ?」
マリアテレサはアレクシスの長広舌に不愉快そうに鼻を鳴らした。
その程度で済んでいる事それそのものが彼の言った指摘の実証となっているのは間違いない。
「まあ、貴方も一応熾天使です。楽園を散策する資格位は認めましょう。
しかし、ゆめ忘れぬ事です。僕は方針を示しました。その事実の意味をお間違いなく。
ええ、僕に命令権等ありませんとも。しかし、絶対にお忘れなく、ね」
「ははは」と軽薄に笑ったアレクシスの様子は実に寒々しく空々しいものだ。
此の世の空虚を煮詰めたような風情で彼はニコリと笑い、マリアテレサに告げるのだ。
「ええ、間違いなく。このアレクシス・アハスヴェール。御身のお言葉は良く良く承知しております故!」
「実に、実に不快な男です」
「では、失礼」と恭しく――いや慇懃無礼な芝居がかった一礼でその場を去ったアレクシスに代わり一人の男がマリアテレサの後ろに立った。
二対四枚の羽を有し、特別な天冠を備えている。熾天使ではないが見るからに別格の神威を纏うその男の表情は実に苦々しいものだった。
「我が君にあれ程の大言を叩くとは。もし御許可が頂けるならばたちどころに彼奴めに挑んで参りましょう!
我が無限の愛を貴方様に捧げ、そのかんばせに微笑みの花を咲かせる事が出来るのならば。この私にとってそれは至高の光栄で――」
「――ああ、うるさい。黙りなさい、カイロス」
放っておけば一時間も続く自身への賞賛をマリアテレサは鬱陶しそうに遮った。
智天使カイロスはアーカディア・イレヴンと父を除けば彼女が個として強く認識する極少ない例外だ。
見目に麗しい彼は最上級に次ぐ天使。堂々と貴族的であり、その立ち居振る舞いは貴公子そのものだ。
しかして、そんな事はマリアテレサにとって自身に侍る最低限の条件に過ぎないのだから、何一つ響いて等居ないのだ。
「大体、出来もしない事を口にするものではありませんよ。
アレクシスはアレでもアーカディア・ファイヴなのです。
まあ、僕からすれば虫のようなものですが――中々器用な所もある。
ふふふ、本当にね。どんな曲芸を持ち合わせているのやら。
それを……貴方如きでは、ねえ?」
「ははは、流石はマイ・レディ。至高の薔薇よ。今夜も何処までも辛辣で――恐悦至極に存じます。
無論、アーカディア・ファイヴ殿に勝つ算段等ありませんとも!
私は単に貴方に愛を捧げると述べたのです。勝てぬまでも腕の一本位はもぎとってみせる。
それで天冠を砕かれ、此の世の塵と変えられようとも――そこに何の後悔がありましょうや。
女神に小指程でも愉悦を捧げられたなら、カイロス如きの命脈など百回捨てても余りある!」
「……………」
マリアテレサは今日一番げんなりとした顔をした。
或る意味で彼女にそんな顔をさせて存在が許されるのは彼だけなのは確かである。
「如何しましたか、我がマリア。夜風に御身を冷やされましたか?」
「口を縫いなさい、もう」
「は。では楽園の仕立て屋を今すぐ叩き起こす事にいたしましょう」
「……これだから嫌なんです、貴方は。何を言っても喜ぶから」
喜色満面のカイロスに対してマリアテレサは虫を払うような仕草で手を振った。
「黙って聞きなさい。貴方の妄言はもう沢山です。
実を言えば、僕としてはこれから――少し面白くなる予感がしているんです」
「……ほう」
「あの子が堕ちた時から、思えば変化は始まっていたのかも。
長い、長い――楽園の微睡みは覚め、皆が現実的にその先を考え始めた事でしょう。
人の尺度における時間と天使のそれは違う。でも、たかだかこの数十年は結果としてとてつもない意味を持ってしまった――」
律儀に言葉を止めたカイロスにマリアテレサは独白気味に言葉を続けた。
「――僕はね、無駄に抗う相手が好きなんです。それがヒトでも天使でも。
僕は蟻を一匹一匹潰すような子供ではありませんから。
最上の舞台、至高の楽園より。オペラ・グラスで喜劇を眺めている位が大人には丁度いいのですから」