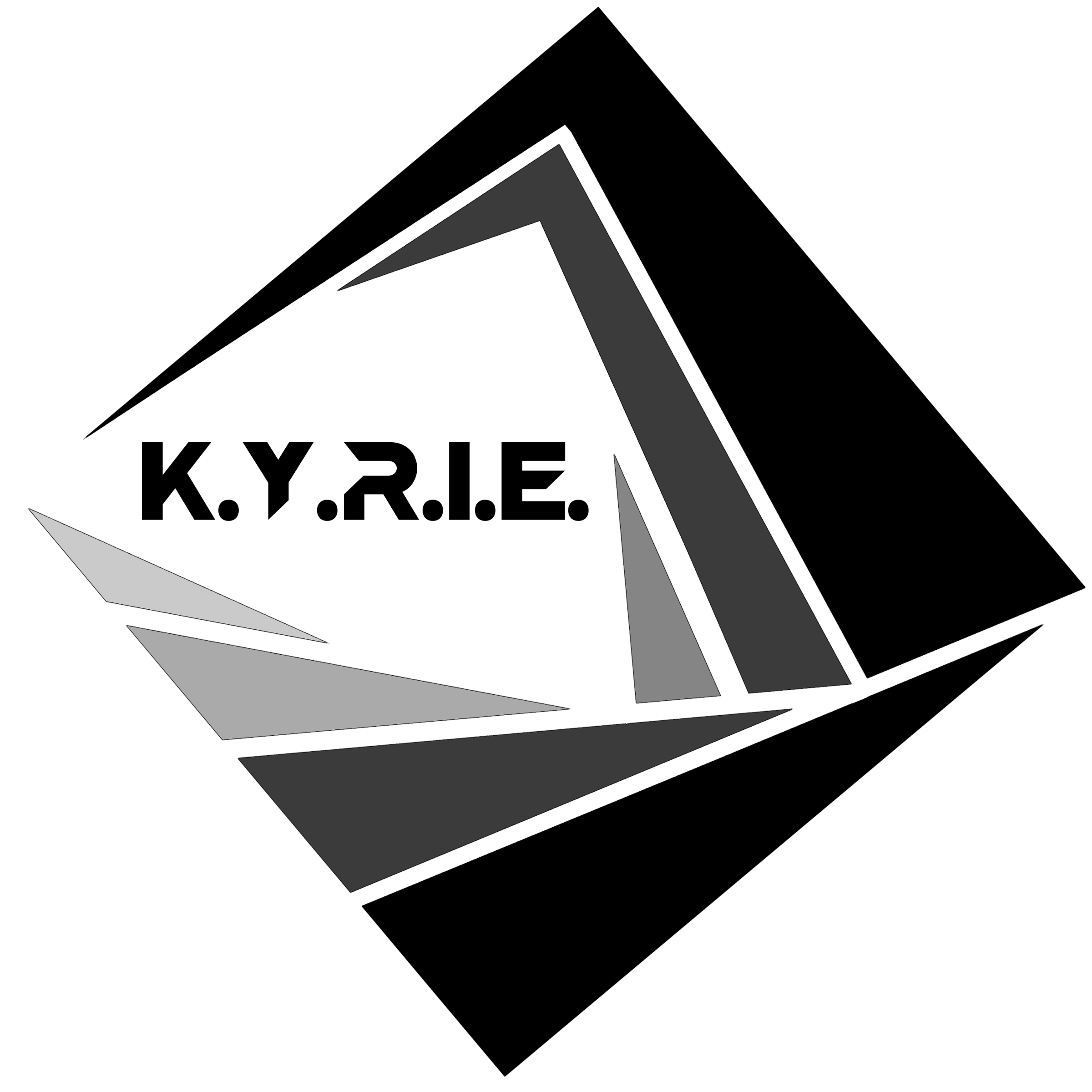白蛇奇譚『ロク』
動物と子供というコンテンツは大量消費社会における鉄板だ。
勿論、それをコンテンツと称するのを気高く気難しく――時に少し人間臭い神様が認める事は無いだろうが、由緒正しい大社にしても維持費が必要なのも現代だ。それにそちらの問題を抜きにしても参拝が増えるのは正しき事と言って良かろう。
桂里奈と『へびちゃん』のコンビは、九頭龍大社ではこれ以上ない程に有名な『名物』と化していた。
弱冠十五歳の巫女、桂里奈。彼女が選抜された理由は内々には『九頭龍大社の巫女たる才覚』が故だが、外から見れば抜擢された彼女は大変な美少女であり、『名物巫女』とその横をついていく蛇が人の耳目を引き付けるは必然であった。
長い黒髪を綺麗に整え、如何にもそれらしい雰囲気のある桂里奈はかくてSNS時代に食い付かれ、落ち着きのあった九頭龍大社は神聖ならぬ理由で時代の寵児となってしまったという訳だ。
(……我はとてつもなく不本意なのだが)
(まあまあ、そう言わないで。皆最近はとっても良くしてくれてるし)
複雑な蛇神の心情を慮らず、既に箱根の街では『へびちゃんと巫女ちゃん』の商品が溢れ、市役所の案内板にも同様のデフォルメキャラクターが記載されているほどだ。全盛期を過ぎたひなびた温泉の街は『へびちゃんと巫女ちゃん』の機会を逃さず、町興しに躍起になっていた。本末転倒な事にキャラクターから本物を知るという逆転現象すら起こっている。
「元気な蛇ちゃんですねー!」
朗らかな笑顔を張り付けたテレビのレポーターが手慣れた調子でマイクを向けた。
「はい! 私とロクちゃんは、とっても仲良しなんです!」
(……ロクちゃん……)
蛇神――第六たる彼をロクと呼び始めたのは桂里奈だが、『ちゃん』は余計だ。
「うふふ。何時も一緒って聞いてますよ?」
「はい! 私は巫女で、大社は蛇神様をお祀りする場所ですから」
もう恒例行事になったテレビの取材だが、今日はローカル放送ではない。
聞き覚えのあるお昼の番組は押しも押されぬ全国ネット。
「ロクちゃんも桂里奈ちゃんが大好きですよねー?」
一瞬だけ「あちゃあ」という顔をした桂里奈の一方、蛇ちゃん……ロクは呆れたようにシャーと鳴く。
それがなんとも「かわいらしい」と更に人気が沸騰しているのは幸か不幸か……
参拝客は増え、ご利益が本当にあるのではないかと「蛇ちゃん」を拝みに来る者すら増えている。
(……現世利益、か)
ロクは現状の有様に辟易としていたが、人を浅ましいと切り捨てる気にもなれなかった。
――元より人とは浅ましさを持つものでございますよ。
人の業を否定する事は人の生を否定する事にございます。
なれば気楽に考えませい。
此の世は神仏の望むよりは浅ましく、人が悪し様に言うよりは美しき哉。
それ、拙僧もこうして供え物のご相伴に預かっていますしね?
――人の世を説法するなら肉を喰らうな、酒に溺れるな。生臭坊主。
――何、問題ございませんとも。精神世界で徳は積んでおりまする。
現世利益という言葉もございます故。
暇な神と差し向かいを為すも功徳でありましょうや?
笑う坊主はそう言って何時も大社の酒を掠め取っていた。
一方の神は毎度苦言を呈しながらも時折顔を出す彼との時間を決して厭うてはいなかった。
目に見えぬものより目に見えるもの。分かりやすくそれっぽいものに縋っているだけ。
分かってはいたとしても、桂里奈と自分がここに居て、世間からの蛇ちゃん呼ばわりもされ。見世物の真似事でもしていれば加護も恩恵も与えられているとするならば、それも良かろうと諦念していた。もはや『へびちゃん』呼ばわりにもすっかり慣れ、声を聞けば振り向くようになってしまったロクが深い溜息をつけば、桂里奈は心配そうな視線を彼に向けていた。
「……ごめんね。疲れちゃった?」
テレビの取材を終えた桂里奈が小さロクはく声に出してロクに問うた。
(全く、聞かれでもしたら面倒だぞ。桂里奈……)
翻して応じたロクは「シャー」という音を発しただけだ。
桂里奈の才覚によるものだろう。何時の頃からか通じ合った二者は近距離ならば声を出さなくても会話が出来る。
周りに人が多いのは知れている。
昔から神秘は面倒事も多い故、ロクは気を付けろと桂里奈に言い含めているのだが……
(あ、ごめん!)
(……まあいい。だが、疲れの方も気にするな。単にうんざりしていただけだからな)
十年近くも一緒に過ごしていれば、ロクが桂里奈という少女を熟知しているのは当然だ。
裏表のない、とても素直な子ども。一緒に過ごしていて安心できるこの少女のことを、彼はいつの間にか好いていた。
――白蛇殿。いっそ人間を好いて共に歩んでみては如何でしょうかな?
――莫迦が。死ね。
(最悪だ。貴様のその顔だけは見たくはなかった)
脳裏に過ぎる糞坊主の得意満面を振り払い、ロクは幾度目か知れない嘆息を吐き出した。
ロクが好いてしまったのは実は桂里奈だけではない。
大社の周りをよくよく周りを見渡してみれば、この場所にはしっかりと縁起が根付き、幸福と平和の輪が広がっている。
「あ、桂里奈ちゃんだ! こっち向いて―!」
「あ、あの。ごめんなさい。ロクちゃんが疲れちゃってて……」
「申し訳ございません。桂里奈は休憩時間でございまして、ご協力願えますと幸いでございます」
スッと割り込んできた禰宜は「早く行きなさい」と指でちょいと合図してくれている。
(良く出来た人間だ。この男も)
「すみません。そこまで気が回らなくて……」
注意を受けた女の声も悪びれていた。
如何にも行楽といった出で立ちでここに居るのだからきっと遠くから来たのだろうと思う。
「シャー……!」
だからロクは桂里奈の腕の中で鎌首を持ち上げ、女の方を向いてやる。
「きゃあ」と声を上げかけ「疲れている」を思い出したように控え目に手を振る女の様はあの頃よりも成熟した現代の、人の善性を感じさせるものだ。九頭龍大社は桂里奈を、そして蛇をこれ以上ない程に大事にしている。
些かの軽薄さは否めないものの、御祭神たる『ロク様』を敬わない人間は此処には居ない。
「……あっ!?」
「……シャー……」
社務所へ戻ろうとして転んだ桂里奈が、見えないクッションに包まれるようにふわりと倒れて。そのまま、慌てたように立ち上がる。
慌てて周囲を見回し、誰もいないことにホッとして。社務所に駆け込むと扉を閉める。
「ロクちゃん……! あんなところで神通力使ったらバレちゃう!」
「気にするな、桂里奈。それにお前が言うな」
「うぐ。確かにさっき声に出して話しかけちゃったけど……
ペットに話しかける人だっているじゃない。
最悪、私が変な子だって思われるだけだからセーフだよ!」
「それはセウトだ、桂里奈」
「ペットとは何事か」と言うだけ面倒なのでロクはそこを構わない。
「第一、我はそれが知れても構わん。我は第六、この社の神ぞ」
「ダメだよ……! 神祇院の人たちに怒られちゃうよ?」
桂里奈が知られずにいるべきは、彼女が人間の世の子だからである。
大神たるロクはこそこそと隠れる理由等無く……いや、桂里奈の為には隠れていた方がより無難だが。
(お前を傷付けるよりは余程マシだ)
これは聞こえないように内心だけで独りごちる。
「――いえ、別に怒りはしませんがね」
二人のやり取りに第三者が参戦した。
眼鏡を押し上げる動きが何ともサマになっているスーツ姿の男。何処にでもいる営業マンのように見えるその男は、神祇院と呼ばれる機関から来た『鈴木』を名乗る人物であった。
「八百万の神々は、なんとも個性豊かでいらっしゃる。それに比べればロク様の何とも」
「黙れ。何をしに来た」
「……これは失礼を」
ロクはこの鈴木のことがあまり好きではなかった。
善人、いや秩序に属する側なのは確かなのだが……どうにも世界の裏を歩く者特有の匂いがした。
神祇院。現代の神秘に関する国家的機関である……と聞いていた。
なんとも鼻につく連中だが、そう思われることを危惧したのか鈴木なる男はいつも腰が異常に低い。それが鼻につくのはもはや、ロクがこの鈴木という男を気に入らないという一点に尽きるのだろう。
ロクは単に嫌っているだけだ。桂里奈に纏わる非日常のリスクを。
(益体も無い話である)
彼が来る時は、厄介ごとがある時だから尚更だ。
「鈴木さん、今日はどうされたんですか?」
「はい。実は最近、おかしな事件がよく起こっていましてね。
しかし調べてみると警察が頼りになる話ではなく――」
「――困りますよ鈴木さん」
社務所の奥からやって来た桂里奈の父は、ロク歓喜の援軍到来だ。
桂里奈に目配せすると鈴木の前にズイッと立ち塞がった彼はロクの期待通りに言い放つ。
「桂里奈は大事な時期なんです。休み前の期末考査だってあるってのに」
「げっ」
「桂里奈? ちゃんと勉強してるよな?」
「し、してるよお父さん……」
「護符の書き方をな」
人の好い――そして勉強をサボりたがる桂里奈は父が居なければ鈴木の話に耳を傾けていた事だろう!
「ロクちゃん!?」
「……お父さんは、今は護符より英単語を書いてくれた方が嬉しいぞ?」
「べ、勉強してきまーす!」
「え、えーと? 桂里奈さん!? 結構私の話は深刻で……」
「はいはい。その話はゆっくりと社務所の方で伺いますからね」
ぐいぐいと鈴木を何処かに連れていく父をそのままに、ロクを伴った桂里奈は部屋に戻る。
蛇のぬいぐるみで埋め尽くされたその部屋は、一般的な女子の部屋としては趣味が偏っていると言わざるを得まい。
床に座り込むと、桂里奈はそのまま机に頭をくっつけてしまう。
「人助けは好きなんだけど……
……鈴木さん、絶対私を神祇院入りさせようとしてるよね」
「そうかもな」
「危険じゃない? 私も女の子だし、あんまり危険な仕事はちょっと……」
「我がどれ程止めても解決に赴き、昨日のノリノリで独自の護符を書いていた奴が何を……」
「そ、そこはいいじゃない! 私にも晴明サマぶりたい時だってあるんだから!」
「何だそのサマ付けは……
ええい、もう似合いではないか、神祇院」
ロクは思わず苦笑して心にもない事を言った。
「ロクちゃん! もう、そんな……」
桂里奈の抗議を遮ったのはメッセージアプリの着信音だ。
「またえすえぬえす、とやらか?」
「あ、うん。高校受験の話。高梨君って、凄い悩みが多いみたいで、あっ……」
高梨君。如何にも男らしき名前が出た時点で、しゅるりとロクは机の上に登り、一口に桂里奈の手のスマホを飲み込む。
「ちょ、ロクちゃん!? スマホ! スマホ!!!」
「繋がりたい症候群め。こんな悪いものは我が溶かしてくれる」
「ダメだってば! ダメ、絶対ダメ。最悪! 返して―!」
「嫌だ」
(許せ、鈴木)
正直を言えばロクは先の鈴木に申し訳なさを感じる事さえあった。
……あの男が嫌いなのはあの男の責ではない。
ロクはただ、今ぷんぷんと怒り自分に強烈に抗議する桂里奈が穏やかな揺り籠の世界で幸福に生きる事だけを望んでいる。
世界の裏。ロクが安寧の世と思っていた世界の裏には、そんな安寧を守る仕組みがある。
かつての陰陽寮の頃よりは、より強固に。
表と裏。しっかりと陰陽のように分かたれた世界の境界は……崩れる気配はない。
ロクはそれに寄与をしているのがあの男を含む神祇院なのだろうと知っている。
「かーえーしーてー!!!」
「ふ、振り回すんじゃない! そんな事をしても我は絶対に吐き出さんぞ!?」
……現代はとても良い時代だ。少なくとも、今のところは。