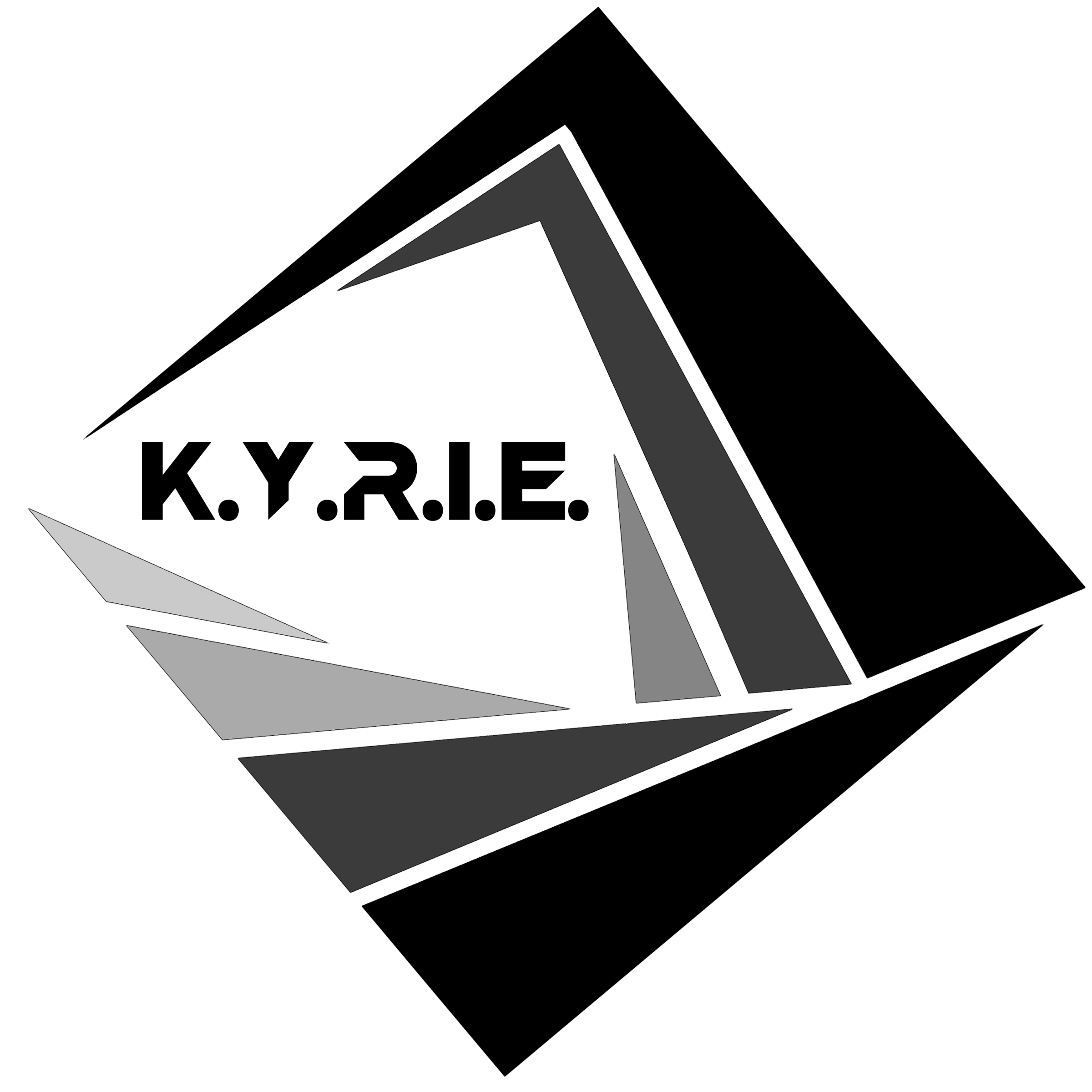いつだって届かない
あの雲が昼夜を覆い隠す。
ふわふわの綿菓子に墨をぶちまけて台無しにしたみたいな雲だ。
今にも落ちてきて全部を圧し潰してしまいそうな、分厚くて真っ黒な空は私達に覆い被さってしまう。
あの雨が大地を、海を叩く。
バケツの中にたっぷりと溜めた汚水をひっくり返したみたいに。
身体に穴が開くかと思うぐらいに痛くて、どんどん身体が重くなって動くのも赦されない雨が降る。
あの波が全てを呑み込もうと迫る。
何も変わらないみたいにゆっくりと、ゆっくりと近づいてくる。
船を、車を、全部押し流して、家を貫いて押し流す。人の身体も悲鳴も命も、全てを呑み込む波が迫る。
まだやってきてないのは、ただ地響きだけだった。
いつも私達が立っている足元で、何か巨大な生き物が低く唸るような音。
それは私達を水底に沈めようと舌なめずりする怪物の音、土地が沈む前兆。
――ああ、全部全部、覚えていた。良く知っていた。
今は未だ少しだけ遠く――でもすぐ傍で確かにあいつが蠢いている証拠。
あいつだ。あいつが、起き上がろうとしている。
起き上がってしまえば、またあいつは何かを、何処かを貪り喰らってしまうのだろう。
好きなだけ、好きなように貪り喰らって、あいつは私達を呑み込んでしまう。
あいつがレイラインを貪り喰らって、そのせいで私達の故郷は沈んでしまったのだ。
刺激しないように遠く、遠く逃げて行く――そうする以外にどうやってあいつから身を護れる方法があるんだろう。
停泊させたペルチスカ。私達の揺り籠、楽園。
その島の端、誰にも気取られないような物陰で頽れるように私はへたり込む。
海の魔女なんて大それた二つ名で呼ばれていても、イェラキは所詮はただの天使に過ぎなかった。
そう、堕天使の力だけでは誰一人として守れもしなかっただけの、ただの天使だ。
あの化け物に、全てを奪われそうになって、人でなしになって逃げただけの――ただそれだけの愚かな天使。
それが、私だった。
片手でもう片方の腕を掴んで自分自身を抱きしめる。そうしないと身体の震えが止まらない。
大きな翼は私の身体を包んで、この怯えも恐怖も覆い隠してくれる。
そうしないと、誰かにばれてしまうから――ばれてしまうことは絶対に避けなくちゃいけないから。
「――怖い」
ぎゅっと眼を閉じてしまえば、言葉が零れ落ちる。
ハッとして、私は顔を上げた。辺りを見渡して――ほっと胸を撫で下ろす。
「良かった、誰にも聞かれてないや」
あぁ、良かった――私は、私だけは誰にもこんな姿を見せるわけにはいかないのだから。
私は海の魔女、居場所のない天使達の止まり木を導く魔女。
私は海の魔女、私がいる限り、全ての滞在者は私の家族。
私は海の魔女、この場に住まう全ての天使達を護り導く義務がある。
私は海の魔女だから、此処に滞在している全ての天使達が一切の不安を二度と感じず生きていけるように。
私自身がこの島を護れるのだと、だから大丈夫だと、そう言い聞かせ続けるために。
そのためには私のちっぽけな本音なんて、絶対に聞かれちゃいけない。
『心海ちゃん、心海ちゃんはきっととっても強い魔女さんになれるよ!
私達を護ってくれる、立派な魔女さんに!』
そう笑って私を応援してくれたあの子の顔はとびきりの笑顔だった。
――うん、きっと、笑顔だった、はずだ。
あの時のあの子の言葉が、声が朧気でも、きっと、笑顔で言ってくれていたような気がする。
「ねぇ……私はとっても強い魔女をやれているのかな」
結局、貴女の手を取れなかった私は、今の私は強い魔女でいれているだろうか。
何度もした自問自答を繰り返し、私は膝を抱えて目を閉じる。
重たい灰色の空、地鳴りに怯えて、その子は私の手を握った。
『怖いねー』
ぎゅって握りしめてくれた手は冷たくて。雨のせいで滑りそうになって、私は強く握り返した。
『でも、心海ちゃんと一緒に居たら安心だー』
そんな風に笑ってたその子は、次の瞬間にはこけてしまった。
滑り落ちる地上、起き上がろうとする友達を海が捕まえる。あの子の身体を呑み込んで連れて行こうと波が押し寄せる。
『心海ちゃん! 助けて――!』
張り裂けそうな悲鳴が、怯えた顔が、伸びた手があっという間に奪われて空を切る。
「い、いや、駄目! 捕まって――!」
叫ぶ声が、伸ばした手が、どちらもあの子には届かない。
ただ、光を嵐に閉ざされた昏い海に呑まれて消えていく。
「……あ、あ、あぁぁぁ――!」
助けられなかった。友達が、顔見知りの大人が、生まれたばかりだろう幼子が、みんな、みんな、全部、波に呑まれて。
あの子を助けられなかった私は、何度も、何度も、何度も、何度も、その光景を繰り返す。
いつも挨拶を交わしていた隣の夫婦が波に呑まれて消えていく。
バイトの後輩が私に向けて手を伸ばして、転げ落ちて沈んでいく。
――いやだ、なんで、どうして、奪われる。天使に殺されるわけでもなくて、ただ土地が崩れて、落ちて。
伸ばした手が届かない。翼を羽ばたかせたって、追いつけない。
ただ、呑まれて沈んでいく。ただ、その人達の悲鳴ばっかりが聞こえてる。
いやだ
いやだ
いやだ
どうして助けられないの? どうして私には力がないの?
どうしてどうしてどうしてどうしてどうしてどうしてどうしてどうしてどうしてどうしてどうしてどうしてどうしてどうしてどうしてどうしてどうして――――
「――――」
誰かの声がする――その声さえも恐ろしく感じて、ぎゅぅと目を閉じる。
身体が揺らされて、声が何かを繰り返す。
「――ラキ」
その声が微かに意味を持って感じられた。
「イェラキ――」
ああ――私の、名前。
「う、うぅ……」
恐る恐る、瞼を震わせて目を開ける。
視界に飛び込んできたのは、肌色だった。
瞬きを繰り返して――顔を上げれば心配そうに此方を見つめる柘榴色の瞳が映る。
両頬に消えない涙の痕を刻んだその人は柔らかく微笑んだ。
「イェラキ、このような場所で眠っていては他の子達に心配されてしまいますよ」
慈しむように、彼女は笑う。まるで、母が子供を愛するように、優しく笑っている。
「ペルセイスさん――ありがとう、少し良くない夢を見ていたみたいだ」
私は、彼女だって護らないといけないのに――私よりも弱い彼女を護らないといけないのに。
それなのに、弱いはずの彼女が私の頬をそっと撫でる。
「くすぐったいよ、ペルセイスさん」
「私のように涙の痕が残り続けても良くないわ」
そっと私の頬を撫でて涙を拭う彼女はそう冗談めかして笑う。
まるで、泣きはらした子供を宥めるみたいで――ううん、もしかしたら今の私は泣き腫らした子供そのものなんだろうか。
「イェラキ――貴女はここで何をしていたの?」
柘榴色の瞳を細めた彼女は小さく首を傾げてそう問いかけてくる。
「海を見てたんだ。あの海に行った、私達の隣人の幾つかは結局戻ってこなかった。
……死んじゃったんだろうね、あいつに殺されたのか、それ以外なのかは分からないけど」
ペルセイスの柘榴色の瞳から目を離して金色の髪を横切り、遠く海に視線を投げかける。
「ペルセイスさんは? もしかして、私のこと探してた?」
「えぇ、貴女の言う通り、光の領域が閉じられたわ。
貴女の気がかりな怪物の活動開始の報告も届いたようね」
「……そっか、ここまでは予想通りだね」
柔らかく微笑みながら告げられた情報の一つずつを呑み込んで、私は一つ息を吐く。
「それに、千獣軍団? のヴィトーって権天使がその怪物を操ろうとして消し飛ばされたと言うわ」
きっと知らない相手であろうと言うのに、悼むように彼女は目を伏せる。
「……そう、うん。そうだろうね」
ヴィトーという天使はトレサリスから名前だけは聞いていた。
クラーケンを操るなんて――そんな無茶をする野心はすごいとは思うけれど、その結末自体は分かり切っている。
「……ふふ、こんなところで蹲ってる場合じゃないね。
光の領域を閉じたってことはいよいよ横須賀に行くつもりなんだろう。
出航しなくっちゃ――ねぇ、ペルセイスさん。少しだけ歩こうか」
杖を手に取ってそっと立ち上がり、彼女の方を顧みた。
そうやってペルセイスに向けた笑顔はいつも通りになってるはずだ。
差し伸べた手を取ったペルセイスも立ち上がる。
「ペルセイスさん。この島は房総半島の切れ端なんだよ。
あいつに――クラーケンにレイラインを食われて崩れ落ちた房総半島の切れ端なんだ。
房総半島、なんて言っても貴女はよく分からないだろうけどね」
二人で歩きながら、何ともなしに話し始めてから思わず苦笑した。
別世界からの来訪者――それがペルセイスだ。彼女に房総半島だとか言っても分かるはずがなかった。
そう、この人は異世界の人だ――ただ、この世界に流れ着いた天使だ。
「私はね、房総半島が沈もうって時に誰一人救えなかった。
ヴァニタスとして人の為に生きてきたんだよ? でも、一人も救えなかった。
自分の手の届く範囲の土地だけ切り取って逃げるしかできなかったんだ」
私の手の届く範囲――この島だけが私が護れたものだった。
「……私は、誰一人救えなかった」
何度その言葉を繰り返すだろう。それでも繰り返す。
それが現実で真実であるのだから。
「私は天使になってまで、逃げて生き残ってしまった。
罪深い――と思う。だからこそ、私は今ここに住んでいる人達を守らないといけないと思うんだ」
「……――イェラキ、貴女と私は似ていますね」
愁うようにペルセイスが笑った。
「……ふふ、貴女よりは背負ったものがずっと少ないと思うけどね」
常秋の国に生まれ育ち、滅びゆく祖国の中で二度と渇かない涙を頬に刻み絶望した女王様。
そんなペルセイスに比べれば、イェラキのそれなんて似ていると言って貰えることさえも恥ずかしい。
ただ――今度こそ、護らないといけないと思う。
この島を、この場所に生きている全ての人達を。
だって、それが私の生き残ってしまった罪で、罪滅ぼしで、私にしかできないことだから。
私が今こうしてこの島で生きているのは――生きていく為だから。
護らなきゃいけない、だって、みんな弱いんだ。
あの化け物に比べたら、みんな弱くて足りなくて、ぷちって殺されちゃって。
皆、皆弱いから、せめて、皆よりずっと強い私が護らなきゃいけない。
人間だって、そう。なんであんなにも弱いのに、まだ私なんかの相手にだってならないのに。
それなのに、あの化け物に立ち向かおうなんて無謀なこと。
そうだよ、だから護らなきゃ、人間にさえも負けちゃう天使もそう。
護らなきゃ、全部、全部護らなきゃ。あいつから――私はその為に出来ることがあるはずだから。
何を犠牲にしたって、何を取り溢したって、私が、私が護らなきゃいけないんだ。
その為になら、何だって、何だってしないと……誰かに恨まれたって、誰かを殺すことになったって構うもんか。
私が護るために、必要な物は何としてでも手に入れなきゃ、何だってしなきゃ。
そうだ、あの人達の言う通り、私は覚悟が足りてなかった。
殺そう、殺してでも、潰してでも、消し飛ばしてでも――私が全部、護るんだ。
彼女達を殺してでも彼女達を、この島に住まう全てを護るんだ――だから。
「行こうか、ペルセイスさん。彼らには悪いけど――光の領域の力は私がもらう。
それが、皆を護るために必要不可欠な事だから」