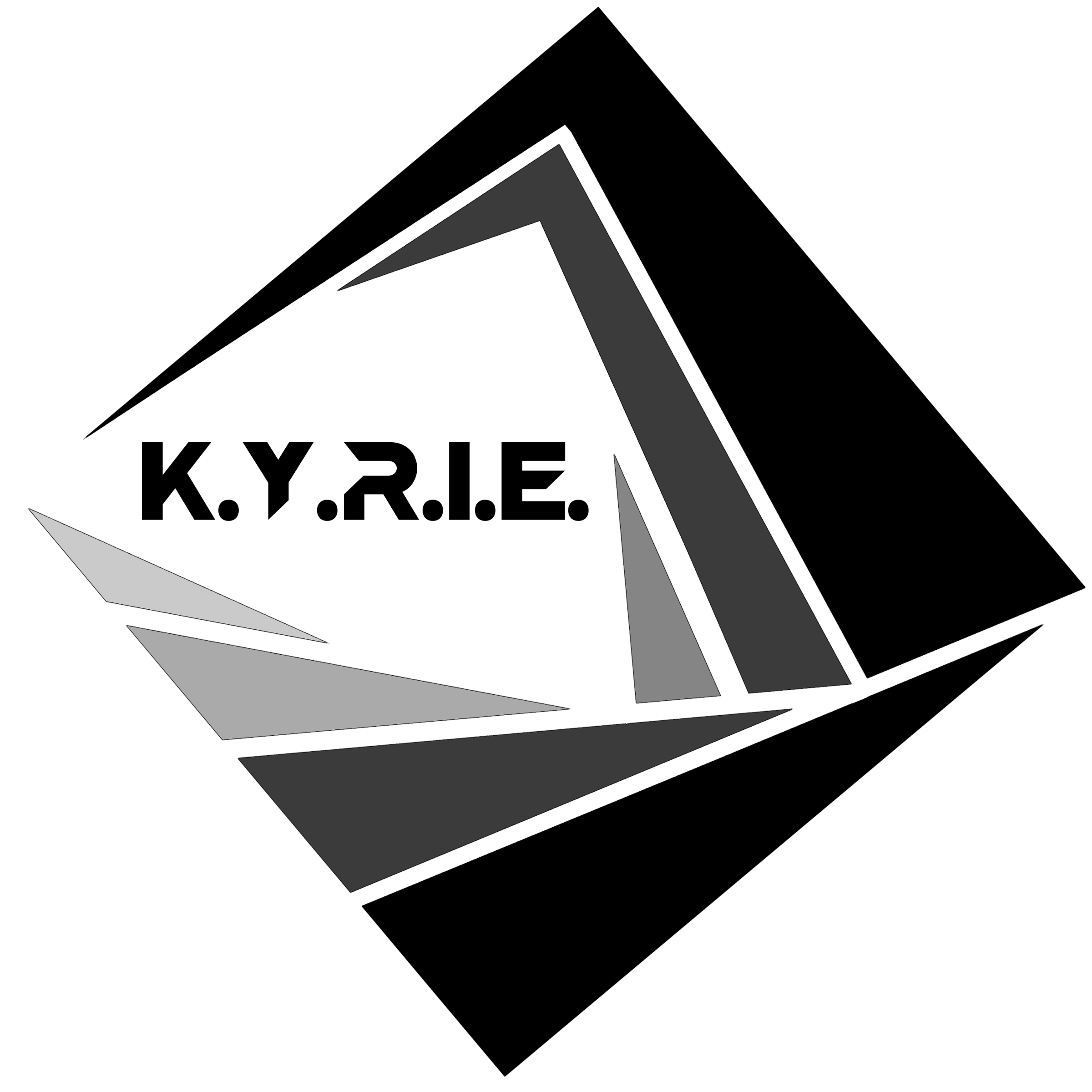厭世と撞着の奇妙な茶会
――御殿場での戦いは続いている。その一報は彼女の胸を痛めたことだろう。
「何てことでしょう。至高たる座に御座すあの方の裁きを受け入れ無いだなんて……。
我々は所詮はあの方々から見れば塵芥に過ぎず、指先一つで消し飛ばされる存在でしかありませんでしょう?
だと、言うのに愚かしくも人の身でありながら、抵抗しつづける。
なんてお労しいのかしら……そうは思いません事? 皆様方」
こてりと首を傾げた女を一瞥してから「さて?」と首を傾いだのはミハイルに付き従っている天使、リーザ・セリーヌ(r2p006775)であった。
彼女はこの地に呼ばれ――いや、正しい言葉遣いをするならば招待状を受け取ったが、如何様にするかは天使の気分次第だ――てやって来ただけである。協力者というわけではないが、単純に眼前の女に興味を持っただけに過ぎないだろう。
「少なくともミハイルには考えがあるんだ。余は同意することはない。
その事に関して物申すつもりもないだろう? 指導者・ヒルデガルド」
「ヒルダとお呼び下さらないかしら、リーザ様」
ティーカップを手にした女の一瞥にリーザは「お近づきになれて嬉しいよ、ヒルダ」とそれだけを返した。
気味の悪い女であるのは確かだ。
女は人間である。天使信仰する終末の徒でさえある。ただのそれだけでありながらも天使達に一定の影響を与えるように見えている。しかし、有効活用するならば、お誂え向きの女だろう、とリーザは踏んでいた。
「ふふ、折角の招待だったんですもの! 応じて良かったです!
でも、そろそろ図書館にも戻らなくてはいけなくって……。親愛なるヒルダ、あなたは何か協力して欲しいことがあってメルたちを呼んだのでしょう?」
こてりと首を傾げたMärchen(r2p004626)はおのれの主を探していた。
何となく、主の痕跡を探る途中に彼女からの招待状を受け取るに至っている。どんな手がかりだって手にしておきたいのが乙女心だからだ。
「ええ、ですがメル様やリーザ様のお手を煩わせたいわけではありませんもの。
他の地上で姿を見られた方々にも招待状を出しましたのよ。理由はただ、そう――終鐘教会をお見知りおき頂きたくて」
「ああ、なんだ! メル達と素敵な関係を築きたかったのですね。分かりました。
じゃあ、これからヒルダが計画することを教えて下さいますか? ふふ、素敵な物語が見られるのであれば楽しみです」
弾むようにそう言ったMärchenにヒルダがゆっくりと後方へと視線を向けた。
背筋をぴしりと伸ばして佇んでいたラティナ・フェルグリム(r2p007327) はヒルダの視線へと小さく頷く。
「指導者がお呼びです」
誰ぞが室内に入ってこようとした、が――それを押し退けて飛び込んで来たのは二人の天使にとっては嫌悪感など抱くわけも無い天使に好かれやすい性質をその身に有した少女だった。
「待って、待って、待って! なんで凪花のこと呼ばないわけ!? 私が一番役に立つでしょ!
ねえ、ヒルダ。知ってるからね、私。小田原でバカゲオミが育ててる繭からそろそろ生まれるんでしょ!?」
淡いエメラルドの瞳を煌めかせ、自慢げにそう言った凪花(r2p007168)にラティナが不機嫌そうな顔を見せた。
「ちょっと――」
「構いませんわ、ラティナ。騒がしくして申し訳ございません、メル様、リーザ様。
この凪花の言う通り、小田原に聖釘を駆使して種を植えておりましたの。
そちらがそろそろ産声を上げる時期――ですけれど、少しばかり栄養が足りないようで……。
ですので、御殿場にお食事に向かう事に致しましたの。事前に調査を他の愛し子達に行わせておきましたわ」
「そうそう。凪花も一緒にしたんだから! 見つからないようにしなよって柘榴が作った魔法道具とか使ったんだから。
完璧よ。ずーっと水面下で私が見ているだなんてマシロ市は思ってもみなかったでしょうからね!」
「言葉が悪いですよ、凪花」
拗ねたような顔を見せた凪花にラティナはふい、と視線を逸らせる。くすくすと小さく笑っていたヒルダにメルは興味深そうに瞳を煌めかせた。
「ね、ね、どうされるのですか?」
「ええ。まだ本体を産み落とすには栄養がたりませんけれど、子機ならば使えますわ。
それらを御殿場に向かわせたく思うのです。
しかし、状況は見ておりますわ。フィエット・アズールの戦場に張り巡らされた霊砡の力は小田原より確認できましょう。
良きタイミングで仕掛けなくては折角の食事も台無しになってしまいますもの。
ああ……勿論、崩天の邪魔は致しませんわ、リーザ様。メル様は我々の活躍をその双眸に焼き付けて頂きたく――」
ヒルダはにんまりと微笑んでから、テーブルに備え付けられた果物を一粒指先で摘まみとった。
「あ、そうだ。ヒルダ、バカゲオミはどうするの?」
ぷちん、と音がしてヒルダの指先を果物の汁が汚す。力が込めすぎてしまったのだろうか、真白な指先は紅色に染まり行く。
「まあ……」
「ヒルダ、大丈夫? 何か心配事?」
彼女は少しばかり困り切った顔をしてラティナが差し出したナプキンでそれを拭った。
「――いいえ? あの子が良い子であれば良いのですけれど」